■■ 第1報告は、黒岩美翔氏(九州大学大学院博士課程)より、「社会責任戦略コントロールに関する一考察:全社的リスクマネジメントERMの可能性」と題する研究報告がなされた。本報告は、財務的コントロールと社会的コントロールの比較考察を通して、マネジメントコントロールやガバナンスシステム、また全社的リスクマネジメントがどこへ向かうのかについて、その手掛りを得ることを目的としている。
■■ 第2報告は、木村眞実氏(沖縄国際大学)より、「自動車解体業への試案MFCAー樹脂を対象としてー」と題する研究報告がなされた。本報告は、MFCAを使用し、静脈産業の生産プロセスには改善の可能性があることを示すことを目的としたものである。
■■ 第3報告は、新茂則氏(中村学園大学)より、「日本版スチュワードシップ・コードとROE投資」と題する研究報告がなされた。本報告は、企業の収益向上に向けた政策と株価動向の実証分析を行うことを目的としている。
■■ 第4報告は、西村明氏(九州大学名誉教授)より、「管理会計におけるデリバティブとものづくり」と題する研究報告がなされた。本報告は、リスク一般ではなく、最も現実的で企業経営に影響するリスクと管理会計との関係を明らかにすることで、現代における管理会計の特徴と問題点の解明を目的としている。
■■ 報告会終了後には開催校のご厚意で、大学周辺の居酒屋で懇親会も開催され,実りある交流の場となった。
足立俊輔 (下関市立大学)
■■ 日本管理会計学会2015年度第2回(第46回)九州部会が、2015年7月25日(土)に九州産業大学(福岡市東区)にて開催された(準備委員長:浅川哲朗氏(九州産業大学))。今回の部会では、九州以外に関西・中部からもご参加をいただくなど、10名近くの研究者や実務家、大学院生の参加を得て、活発な質疑応答が展開された。
■■ 第1報告は、田尻敬昌氏(九州国際大学)より、「組織スラックとフィードフォワード・コントロール―スラック形成とその戦略的展開」と題する研究報告がなされた。本報告は、組織スラックをフィードフォワード・コントロールの観点から再検討することを目的としたものである。
■■ 第2報告は、緒方光行氏(福岡常葉高等学校)より、「キャリア教育の視点に立った管理会計の指導法について」と題する研究報告がなされた。本報告は、平成25年度の高等学校学習指導要領の改訂により、新たに導入された「管理会計」の現場での現状と課題を説明した上で、キャリア教育で重視されるようになった観点別評価の実態を紹介したものである。
■■ 第3報告は、招聘講演として、今井範行氏(名城大学)より、「デュアルモード管理会計とプロアクティブスラック―予算スラックの順機能性に関する一考察―」と題する研究報告がなされた。本報告は、逆機能的な予算スラックとは異質の順機能的な予算スラックとして、トヨタ的業績管理会計の事例を取り上げ、その要諦について「プロアクティブスラック」として概念化をはかるとともに、その管理会計的意義について考察を加えたものである。
足立俊輔 (下関市立大学)
■■ 日本管理会計学会2015年度第1回(第45回)九州部会が、2015年4月18日(土)に中村学園大学(福岡市城南区)にて開催された(準備委員長:水島多美也氏(中村学園大学))。今回の部会では、九州以外に関西・関東からもご参加をいただくなど、10名近くの研究者や実務家の参加を得て、活発な質疑応答が展開された。
■■ 第1報告は、谷守正行氏(専修大学)より、「サービス業における原価計算に関する研究―銀行のポストABCアクションリサーチを通して―」と題する研究報告がなされた。本報告は、わが国の銀行で導入されてきたABCによって算出される顧客別情報の問題点を解決するために、より現場感覚に合う顧客別情報を提供するABCの配賦方法をアクションリサーチに基づいて提示することを目的としたもの
■■ 第2報告は、宮地晃輔氏(長崎県立大学)より、「造船業における人的資産・組織資産の高度化への取組みと課題」と題する研究報告がなされた。本報告は、長崎県佐世保地域で行われている造船人材活性化への取り組みについて、その現状と課題を明らかにしようとしたものである。
■■ 第3報告は、西村明氏(九州大学名誉教授)より、「企業リスクマネジメントと機会/機会原価統制システム」と題する研究報告がなされた。本報告は、近年グローバル企業が抱えるリスクに対して管理会計が果たすべき役割について、利益機会とリスク管理の構造から明らかにしようとしたものである。
■■ 研究報告会の後、総会が行われた。総会では前年度の会計報告と今年度の九州部会開催の議題が出され、双方とも承認を得た。今年度の九州部会については、第46回大会は7月25日に九州産業大学にて、第47回大会は福岡大学にて11月に開催予定である。報告会終了後、開催校のご厚意により懇親会が開催された。懇親会は有意義な研究交流の場となり、盛況のうちに大会は終了した。
足立俊輔 (下関市立大学)
■■ 日本管理会計学会2014年度第44回九州部会が、2014年11月22日(土)に西南学院大学(福岡市早良区)にて開催された(準備委員長:高野学氏(西南学院大学))。今回の部会では、九州以外に関西・関東からもご参加をいただくなど、20名近くの研究者や実務家の参加を得て、活発な質疑応答が展開された。
■■ 第1報告は、吉田栄介氏(慶應義塾大学)および徐智銘氏(慶應義塾大学大学院商学研究科後期博士課程)より、「日本企業の品質コスト志向性:実態調査に基づく探索的分析」と題する研究報告がなされた。本報告は、高品質と低コストの両立を志向するといわれてきた日本企業の管理活動実態について、郵送質問票調査(有効回答
■■ 第2報告は、高野学氏(西南学院大学)より、「東日本大震災以降の電気事業における総括原価方式の役割」と題する研究報告がなされた。本報告は、電気事業で電気料金総収入を算定する際に、従来から採用されてきた「総括原価方式」が、東日本大震災による福島第一
■■ 第3報告は、浅川哲郎氏(九州産業大学)より、「オバマ改革以降の病院マネジメントシステムの変化について」と題する研究報告がなされた。本報告は、アメリカのオバマ政権によって2010年に立法化された医療保険制度改革法(ACA)により、病院規模や病院組織に変化が生
■■ 第4報告は、田坂公氏(久留米大学)より、「フルーガル・エンジニアリングと原価企画」と題する研究報告がなされた。本報告は、インドで考案されたフルーガル・エンジニアリング(FE)と原価企画の関連性を検討し、開発の現地化の新たな方向性を考察しようとしたものである。報告は、原価企画とFEの関係性を、(1)支援体制
■■ 研究報告会終了後、懇親会が西南クロスプラザ(ゲストルーム)にて開催された。懇親会は有意義な研究交流の場となり、盛況のうちに大会は終了した。
下関市立大学 足立俊輔
■■ 第1報告は、角田幸太郎氏(別府大学講師)より、「英国プロサッカークラブにおける人的資源の会計と管理の事例研究」と題する研究報告がなされた。報告は、プロサッカークラブの人的資源の測定・評価の先行研究(Morrow(1992)、Risaliti and Verona(2013)など)が財務会計の分野が中心であることを指摘した上で、人的資源に関する管理会計/マネジメント・コントロールの側面からの分析を目的としたものである。報告は文献研究のほか、英国・日本のプロサッカークラブへのヒアリング調査に基づいたものである。
■■ 第2報告は、黒瀬浩希氏(九州大学大学院博士後期課程)より、「グループ子会社におけるCSRマネジメント・コントロールの事例研究」と題する研究報告がなされた。本報告は、グループ子会社(飲料製造・販売グループの物流子会社X社)におけるCSRマネジメント・コントロールについての事例研究である。具体的には、Epstein and Roy(2001)やDurden(2008)、細田・松岡・鈴木(2013)の先行研究をグループ子会社に適応した場合、フォーマル・コントロールシステム(FCS)やインフォーマル・コントロール・システム(ICS)にどのような影
■■ 第3報告は、木村眞実氏(沖縄国際大学准教授)より、「自動車静脈系サプライチェーンへの試案MFCA」と題する研究報告がなされた。本報告は、自動車の静脈産業(使用済自動車の解体・製錬を行う業者)に試案MFCA(マテリアルフローコスト会計)を適応することで、廃棄物の削減と資源の有効利用につなげる生産プロセスの検討を目的としたものである。具体的には、使用済自動車の付着物ワイヤーハーネスに解体加工を施すプロセスに試案MFCAを適応し、そのプロセスの「見える化」を図ろうとしたものである。
■■ 第4報告は、西村明氏(九州大学名誉教授)より、「企業経営戦略とリスクマネジメント」と題する研究報告がなされた。報告は、企業が抱える様々なリスクの態様を、経営活動全体の中に位置づけて管理するために、管理会計がどのように貢献することができるかを明らかにしようとしたものである。
■■ 研究報告会の後、総会が行われた。総会では、前年度の会計報告と今年度の九州部会開催の議題が出され、双方とも承認を得た。また、次回の九州部会は、11月22日に西南学院大学にて行われることが情宣された。
下関市立大学 足立俊輔
投稿ナビゲーション
The Japanese Association of Management Accounting
 ■■ 日本管理会計学会2015年度第3回(第47回)九州部会が、2015年11月7日(土)に福岡大学(福岡市城南区)にて開催された(準備委員長:飛田努氏(福岡大学))。今回の部会では、九州以外に中部・関東からもご参加をいただくなど、15名近くの研究者や大学院生の参加を得て、活発な質疑応答が展開された。
■■ 日本管理会計学会2015年度第3回(第47回)九州部会が、2015年11月7日(土)に福岡大学(福岡市城南区)にて開催された(準備委員長:飛田努氏(福岡大学))。今回の部会では、九州以外に中部・関東からもご参加をいただくなど、15名近くの研究者や大学院生の参加を得て、活発な質疑応答が展開された。
 外の潜在リスクを予見することが難しい。そのためトヨタでは、為替レートや販売数量など収益ドライバーの前提を「保守的」な水準に置き換えた利益計画を提示して、その保守的に置き換えた分の利益減少分を、追加的なコスト低減策の策定でカバーすることが求められている。報告では、当該コスト低減策により、順機能的な予算スラックとしてプロアクティブスラックが形成されていることが、設例や図表を用いて紹介されている。
外の潜在リスクを予見することが難しい。そのためトヨタでは、為替レートや販売数量など収益ドライバーの前提を「保守的」な水準に置き換えた利益計画を提示して、その保守的に置き換えた分の利益減少分を、追加的なコスト低減策の策定でカバーすることが求められている。報告では、当該コスト低減策により、順機能的な予算スラックとしてプロアクティブスラックが形成されていることが、設例や図表を用いて紹介されている。 である。
である。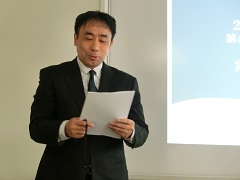
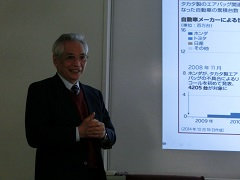
 会社数130社、回収率15.3%)の結果に基づいて考察を加えたものである。
会社数130社、回収率15.3%)の結果に基づいて考察を加えたものである。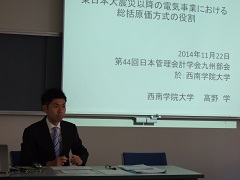 原発の事故により新たに発生した原発事故費用を考慮するようになってから、どのように役割変化がみられたのかについて考察を加えたものである。
原発の事故により新たに発生した原発事故費用を考慮するようになってから、どのように役割変化がみられたのかについて考察を加えたものである。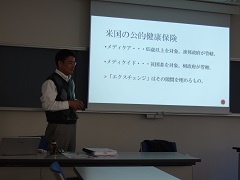 じているのか、また、病院の経営形態にどのような変化がみられているのかについて、報告者の現地調査に基づいて明らかにしようとしたものである。
じているのか、また、病院の経営形態にどのような変化がみられているのかについて、報告者の現地調査に基づいて明らかにしようとしたものである。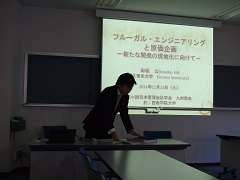 と(2)設計開発プロセスの面から明らかにしている。
と(2)設計開発プロセスの面から明らかにしている。 ■■ 日本管理会計学会2014年度第43回九州部会が、2014年7月26日(土)に九州大学(福岡市箱崎)にて開催された(準備委員長:大下丈平氏(九州大学教授))。今回の部会では、九州以外に関西・中部・関東からもご参加をいただくなど、20名近くの研究者や実務家の参加を得て、活発な質疑応答が展開された。
■■ 日本管理会計学会2014年度第43回九州部会が、2014年7月26日(土)に九州大学(福岡市箱崎)にて開催された(準備委員長:大下丈平氏(九州大学教授))。今回の部会では、九州以外に関西・中部・関東からもご参加をいただくなど、20名近くの研究者や実務家の参加を得て、活発な質疑応答が展開された。
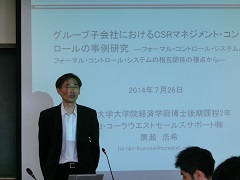 響が生じるかを明らかにしたものである。
響が生じるかを明らかにしたものである。
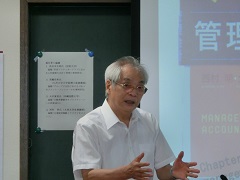 の開発・実現から企業価値創造に向かうプロセスが明らかにされた。その上で、リスクを経営管理全体の中に位置づけるためには、戦略リスク・経営財務リスク・業務リスクそれぞれに対応したリスク対応が必要であり、そのためにはリスク尤度と期待損失額の関係でリスク態様を描き、そのリスクの経営対応を具体的に検討する。報告者は以上のプロセスを、企業が実際に抱えるリスク問題と関連させながら明らかにしている。
の開発・実現から企業価値創造に向かうプロセスが明らかにされた。その上で、リスクを経営管理全体の中に位置づけるためには、戦略リスク・経営財務リスク・業務リスクそれぞれに対応したリスク対応が必要であり、そのためにはリスク尤度と期待損失額の関係でリスク態様を描き、そのリスクの経営対応を具体的に検討する。報告者は以上のプロセスを、企業が実際に抱えるリスク問題と関連させながら明らかにしている。