日本管理会計学会2025年度第3回フォーラム(後援:川越商工会議所)は,2025年11月29日(土)14時00分から16時40分まで,東京国際大学川越第1キャンパスにおいて対面形式にて開催された。開会に先立ち,本学会会長・﨑章浩氏(東京国際大学)よりご挨拶を賜り,引き続き,奥倫陽氏(東京国際大学)の司会によりプログラムが進行した。

﨑章浩会長挨拶
本フォーラムでは,特別講演として笛木吉五郎氏(笛木醬油株式会社 代表取締役社長 十二代目当主)をお迎えし,あわせて伊藤和憲氏(東京国際大学)および宮地晃輔氏(長崎県立大学)による研究報告の計3件が行われた。
当日は,45名の参加があり,いずれの特別講演・研究報告に対しても活発な質疑応答が交わされ,大変有意義な議論が展開された。さらに,閉会時にはスイスより来日された米国管理会計士協会(Institute of Management Accountants:IMA)グローバル理事 Nina Michels-Kim氏より挨拶を賜った。フォーラム終了後には懇親会も催され,参加者間の親睦が一層深まった。盛況のうちに本フォーラムは無事に閉会した。
〔特別講演〕
◎講演者:笛木吉五郎氏(笛木醬油株式会社 代表取締役社長 十二代目当主)
◎講演題目:235年続く老舗醤油蔵によるマネジメントシステムを活用した地域活性化の取り組み

笛木吉五郎氏による特別講演
本講演では,創業235年の醤油蔵を継承した笛木氏が,事業承継後の経営改革と持続性向上に向けた取り組みを紹介した。笛木氏が事業を引き継いだ2017年当時,同社は8期連続赤字であり,組織は「皆がバラバラに綱引きをしている」状態であった。経営相談を行ったコエドビールの朝霧社長から「好きなことをやる姿を見せるべき」という助言を受け,経営者としての姿勢を見直したことが改革の出発点となった。
コロナ禍による資金繰りの悪化は,財務基盤の重要性を再認識する契機となり,同社は高収益型事業構造への変革を本格化させた。具体的施策として,経営計画書の策定と発表,毎月の部門別月次数値ミーティングの実施,財務情報の全面的な「見える化」を挙げた。従来は開示されていなかった数値を社員に共有し,自ら改善策を考える文化が醸成された。
業績改善に大きく寄与した取り組みとして,①過去50期分の決算書分析,②全商品・全顧客の粗利率分析と値決め改革,③期間を決めてすべての購買の決裁を社長決裁に,④会議や会合参加など「やめること」の決定,⑤金融機関との信頼関係強化が紹介された。とくに粗利率管理の徹底は利益体質の改善に直結した。
また同社は,女性活躍推進や柔軟な働き方の整備を通じ,組織の多様性と持続性の向上にも積極的に取り組んでいる。2019年には,食べる・学ぶ・買う・遊ぶことができる体験型複合施設「金笛しょうゆパーク」をオープンし,観光・教育・体験を融合させた新たな価値創造に挑戦している。現在は16か国に輸出するなど,伝統産業の枠を超えた成長を続けている。
〔研究報告〕
第1報告
◎報告者:伊藤和憲氏(東京国際大学)
◎報告題目:中小企業における管理会計の事例
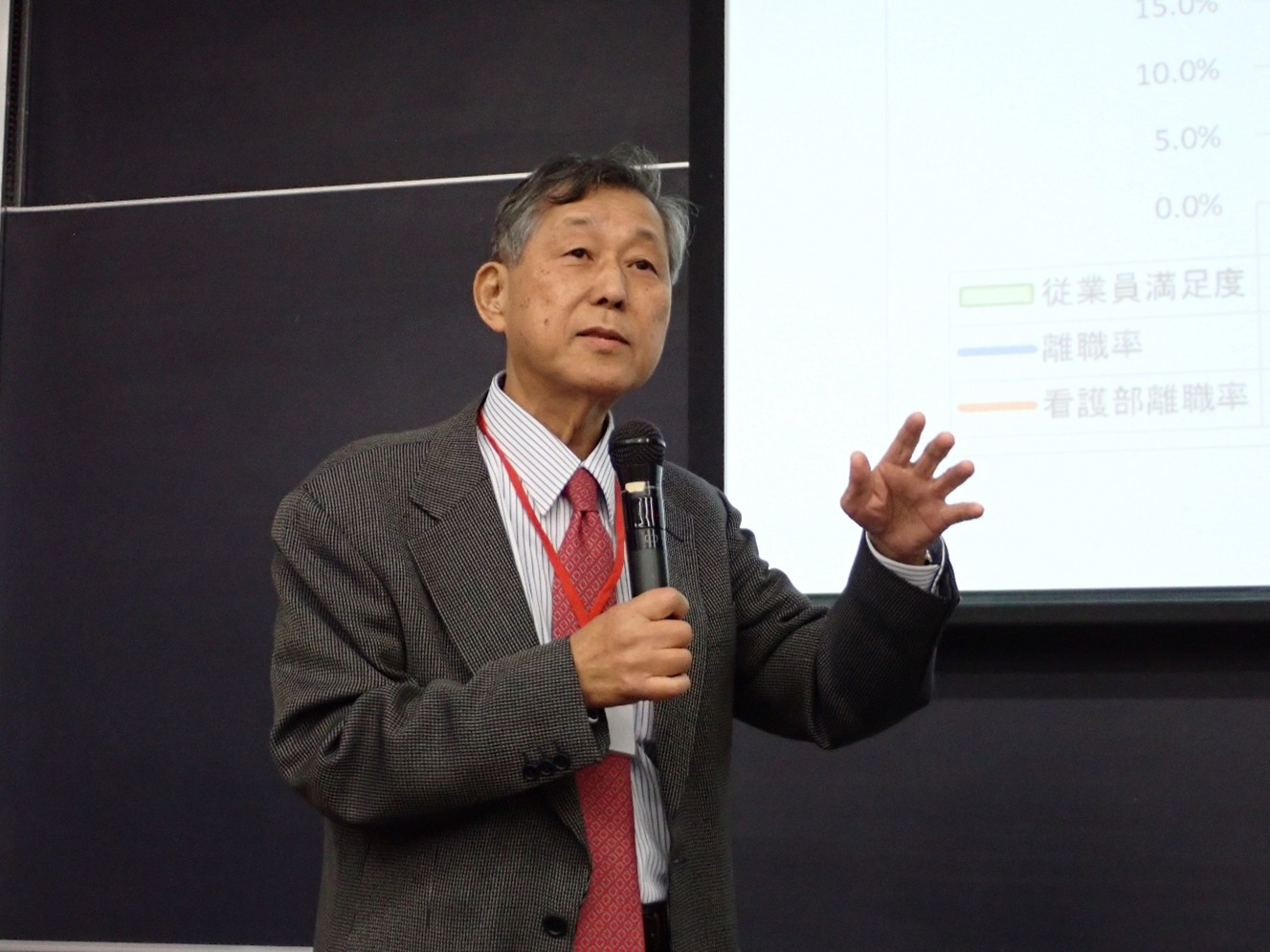
伊藤和憲氏による研究報告
本報告では,中小企業に役立つ管理会計として,BSCを活用している中小病院であるベトレヘムの園病院の事例報告が行われた。伊藤氏は同病院で使用されているBSCに対して修正提案を行いつつ,リサーチサイトが感じたBSCの効果を明らかにした。
リサーチサイトであるベトレヘムの園病院(療養型病院)の概要とBSCの導入と展開について報告された。BSC導入目的は職員同士のコミュニケーションを促してベクトル合わせをすることであった。当時は離職率が25%~30%と高い推移であった。
BSCの導入と展開として2016年にBSC試行(事務部長単独)から始まり,2017年にBSC導入,2018年にBSC一部修正,2019年に電子カルテ導入,2022年にコロナ対応とBSC,そして2023年に社会的課題への対応を行った。BSC導入を進める中で,伊藤氏が導入支援を病院の事務部長から依頼され,BSC導入上の間違いを正したり,電子カルテ導入とBSCを連動させたり,診療部へのカスケード方法,看護部のスキル測定などの提案を行ったことを報告された。
最後にBSC導入成果を報告された。同病院は患者満足度が低くて,離職率が高いという問題を有していた。BSC導入前の2015年は従業員満足度が72.1%,離職率が23.6%であった。BSC導入後は従業員満足度が向上し,離職率が低下する趨勢を示し,2022年のそれぞれの値が86.3%,9.0%となった。ベトレヘムの園病院の事務部長はBSCによって離職率が激減し,従業員満足度向上につながったのではないかと言及されているという。
第2報告
◎報告者:宮地晃輔氏(長崎県立大学)
◎報告題目: 管理会計研究者と税理士法人が連携した地域企業人材に対する管理会計教育の可能性―新しい地方創世の展開を視野に入れて―

宮地晃輔氏による研究報告
本報告では,管理会計研究者と税理士法人の連携により作成された中小企業向け管理会計テキスト『伴走者になるための会計入門』(中央経済社,2025)を用い,地域企業人材への管理会計教育を実施したアクションリサーチの成果が紹介された。対象となったA社は,BtoB型の事業展開を行っており,製造企業を主たる顧客としている。業績は安定しているものの後継者がおらず,技術系中心の人材構成から部門長層の会計知識が不足していた。宮地氏は将来の経営者候補として育成する目的で,部門長4名に対する会計管理能力(係数管理能力)の基礎を習得することを目的として会計教育研修を実施した。
宮地氏は2018年からA社の顧問を務め,経営会議にも継続的に参加しており,日常より,A社における受注,生産,工事,クレーム・不適合,原価管理に対して意見交換やサポートを行っている。宮地氏が研修講師を務めることで,同社に最適化されたオーダーメイド型の研修が可能となる。
結論として,地方大学に所属する管理会計研究者は,管理会計手法を地域の中小企業や地方自治体の経営実践や実務に普及させる機会に比較的,好条件を有することから地方創生に貢献できる可能性も高い。また,本研修を実施するにあたり各部門長を通常業務から切り離す必要があり,A社にとってこのことは決して簡単なハードルとはいえない,このハードルをこえるためには経営者の強い思いと決断が必要になる点を強調された。
文責 梅田 宙 (高崎経済大学)






