2025年11月28日 尾花忠夫(愛媛大学)
日本管理会計学会2025年度第2回関西・中部部会は、2025年11月15日(土)に愛媛大学(愛媛県松山市)を主催校として開催された。部会準備委員長から進行方法の説明があり、続いて窪田祐一関西・中部部会長から開会の挨拶が行われた。
今回の部会は対面(来会)とWeb(Zoom)を併用したハイブリッド形式であり、対面参加者は10名、Web参加者は7名であった。以下、各報告の概要と特別講演について簡単に紹介する。
第一部〔研究報告〕 司会:尾花忠夫氏(愛媛大学)
第1報告
報告者:近藤隆史氏(京都産業大学)
論題 :「創造的タスクにおけるインセンティブ効果の条件依存性:NKモデルを用いた数
値実験」
近藤氏による報告は、創造的タスクにおけるインセンティブの効果を数値実験により定量的に分析することを目的とし、創造的な成果に対するインセンティブ設計の課題について、シミュレーションを通じた理論的な考察を提供した。
先行研究は、インセンティブが量を促すと発散を助長する一方で質が低下し、質を促すと収束を促す一方で提出行動が抑制されるという「発散と収束のトレードオフ構造」を指摘している。本研究の目的は、このトレードオフを解消し、統合的なパフォーマンスを高めることが期待されるハイブリッド・インセンティブの効果を、タスクの複雑さ(低・中・高の3水準)や探索戦略の違い、さらには内在するバイアス(心理的・構造的)を考慮した上で検証することにあった。検証手法として、管理会計分野では珍しいNKモデルを用いた数値実験が採用された。NKモデルを用いることで、タスクの複雑性を操作し、発散と収束の探索を再現できるランドスケープが構築され、ランダム探索を行うエージェントの成果(質、量、複合指標CP)が測定された。
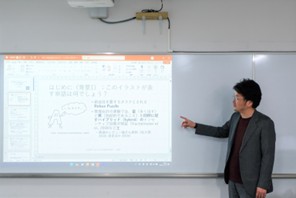 結論として、ハイブリッド・インセンティブの効果は「バランス調整として控えめに理解しておく」べきであり、相乗効果は単純なタスクに限定される可能性が示された。中程度の複雑さにおける不安定性や心理的バイアスに対処し、その効果を最大限に引き出すためには、共通理解の徹底や追加的な調整操作が必要であると提言された。本研究は、ラボ実験では操作や誘発が難しい要因をモデル化することで、インセンティブ行動との関係を体系的に理解する仕組みを提供した点で、理論的な貢献を果たしている。
結論として、ハイブリッド・インセンティブの効果は「バランス調整として控えめに理解しておく」べきであり、相乗効果は単純なタスクに限定される可能性が示された。中程度の複雑さにおける不安定性や心理的バイアスに対処し、その効果を最大限に引き出すためには、共通理解の徹底や追加的な調整操作が必要であると提言された。本研究は、ラボ実験では操作や誘発が難しい要因をモデル化することで、インセンティブ行動との関係を体系的に理解する仕組みを提供した点で、理論的な貢献を果たしている。
第2報告
報告者:森本和義氏(羽衣国際大学)
論題:「サステナビリティ経営と管理会計」
森本氏の報告は、従来の管理会計研究が株主価値最大化と事業部長の業績目標の整合性をいかに確保するかという課題から、現代的なサステナビリティの要請へと関心を移してきた経緯を示した。従来、プリンシパル=エージェント関係を前提に、最適なインセンティブ設計が探求され、会計利益から導かれる残余利益(RI)が、事業部長に最適投資を誘導する最適指標とされた。しかし、現代では「Profit、People、Planet」というサステナビリティの要請が強まる中、金銭的インセンティブだけでは不十分であるとの問題意識が示された。ボールズのモラルエコノミーに基づき、金銭的誘因の過度な利用が倫理的、他者考慮的な動機を弱める点が指摘され、日本の自動車産業に見られる互恵的な慣行が非金銭的動機の重要性を示す事例として紹介された。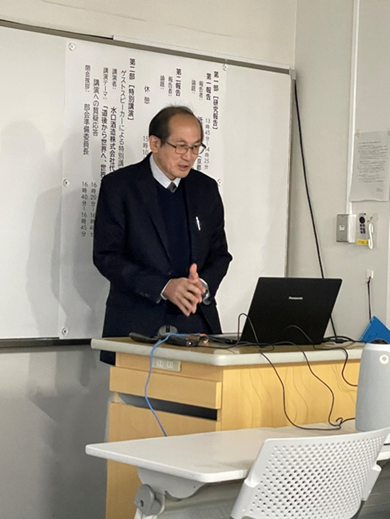 さらに、サステナビリティにおける取締役会の役割に焦点を移し、現行のコーポレートガバナンス・コードが株主第一主義の影響を残しつつもサステナビリティを課題としている点、またエージェンシー理論と対立するスチュワードシップ理論が経営者のエンパワーメントを重視する点が論じられた。株式会社をコミットメントの装置と捉えるメイヤーの議論や、CSR経営を許容する日本の会社法の例外規定も確認された。
さらに、サステナビリティにおける取締役会の役割に焦点を移し、現行のコーポレートガバナンス・コードが株主第一主義の影響を残しつつもサステナビリティを課題としている点、またエージェンシー理論と対立するスチュワードシップ理論が経営者のエンパワーメントを重視する点が論じられた。株式会社をコミットメントの装置と捉えるメイヤーの議論や、CSR経営を許容する日本の会社法の例外規定も確認された。
結論として、今後の管理会計は物的資本だけでなく、自然資本や労働者の福祉、コミュニティへの貢献といった非金銭的資本を取り込む必要があると強調され、経済人モデルと自己実現人モデルの共存、従業員のエンパワーメント、非金銭的インセンティブ設計が課題であると示された。
第二部〔特別講演〕 司会:尾花忠夫氏(愛媛大学)
講演者:水口皓介氏(水口酒造株式会社 代表取締役社長)
講演テーマ:「道後から世界へ、世界から道後へ 水口酒造の挑戦」
特別講演では、地域密着型酒造会社が直面する課題、グローバル展開に向けた具体的戦略、そして現代的な経営手法の導入について語られた。まず、企業の強みとして、道後温泉に隣接する希少な立地と、愛媛県産「さくらひめ酵母」を用いた日本酒が海外コンテストでも高く評価されている点が挙げられた。また、日本酒以外にもクラフトビール、焼酎、ジンなど多様な製品を製造し、長期サイクルの日本酒事業を補完していることが説明された。
経営課題としては、売上の約85%が松山市内(道後周辺を含む)に依存している点が最大の弱みであり、地域外・海外への販路拡大が不可欠と説明された。そのため、財務会計中心の経営から脱却し、原価管理や予実管理を可能とする管理会計への移行を進めているとの説明があった。また、近年の原材料費や最低賃金の上昇に対応するためにも、迅速な経営判断を支える管理会計の重要性が強調された。このことに加え、外部人材の登用や学生インターンの活用、社内のDX化やプロジェクト管理能力を組織に浸透させる取り組みも紹介された。
 今後の水口酒造の戦略として、「道後から世界へ、世界から道後へ」というビジョンのもと、輸出増加を通じてブランド価値を高め、最終的には海外顧客を道後に誘客すること、長期的には、酒蔵の一部移転を行い、体験型施設・テーマパーク化の構想、高付加価値な観光体験の提供と収益拡大を図る方針が示された。また、科学的データと杜氏の官能評価データを蓄積し、品質の再現性を高めることが今後の重要課題であると述べられた。
今後の水口酒造の戦略として、「道後から世界へ、世界から道後へ」というビジョンのもと、輸出増加を通じてブランド価値を高め、最終的には海外顧客を道後に誘客すること、長期的には、酒蔵の一部移転を行い、体験型施設・テーマパーク化の構想、高付加価値な観光体験の提供と収益拡大を図る方針が示された。また、科学的データと杜氏の官能評価データを蓄積し、品質の再現性を高めることが今後の重要課題であると述べられた。
以上の自由論題2報告、講演会のいずれにおいても報告後の質疑応答では参加した研究者と報告者との間で活発な議論が交わされ、盛会のうちに、全プログラムが終了した。






