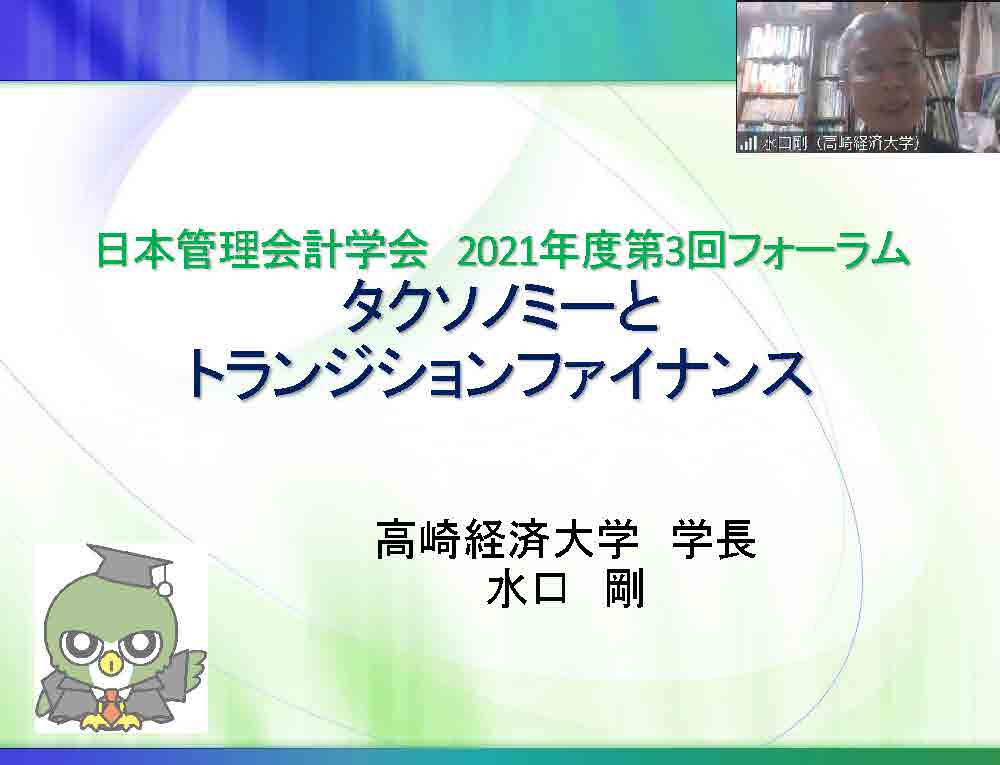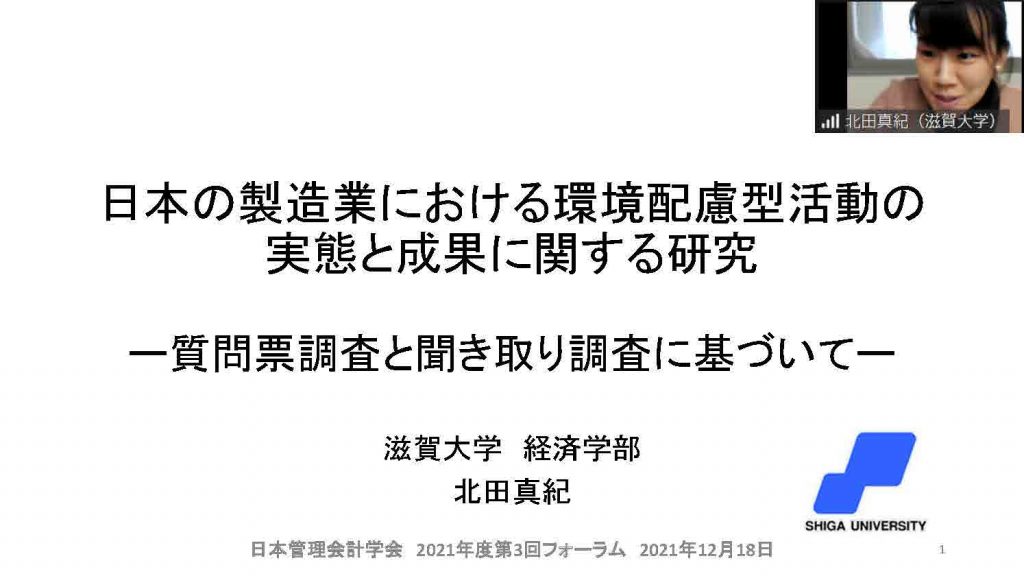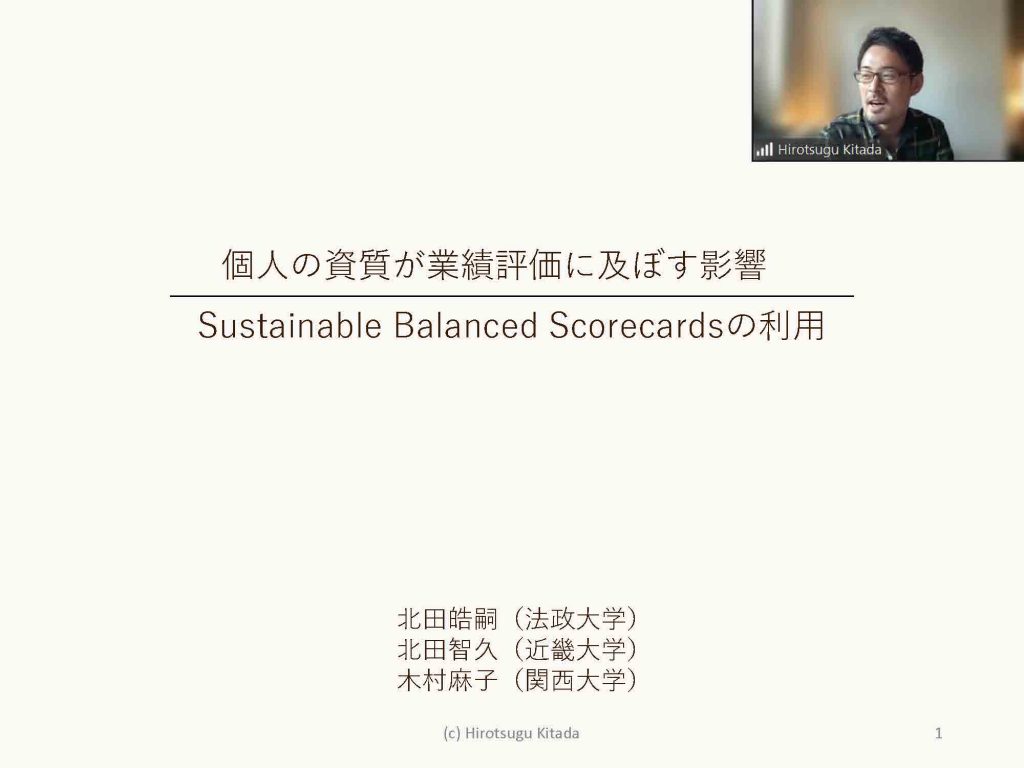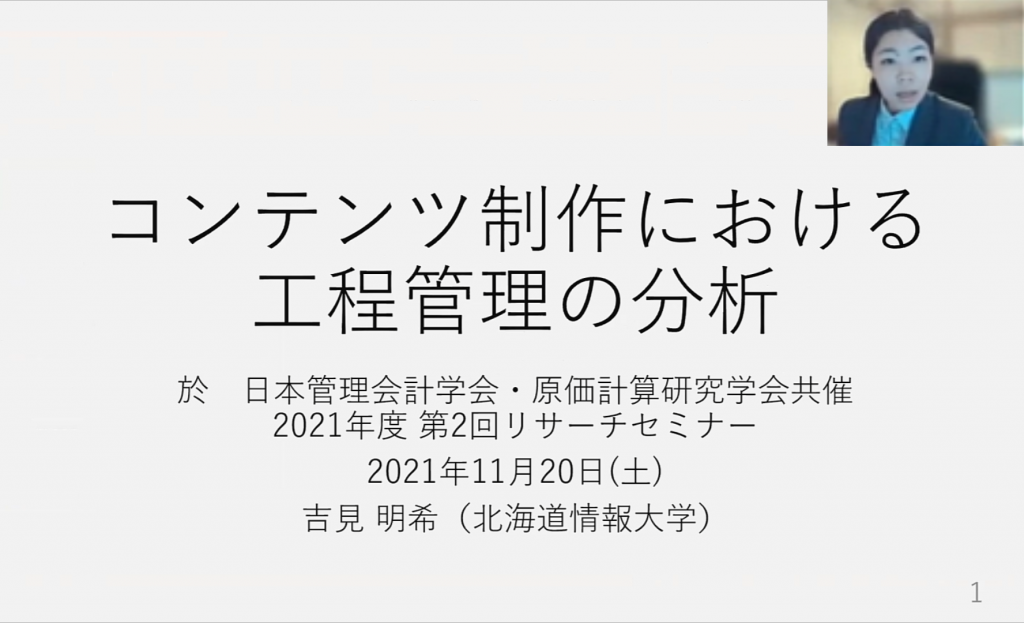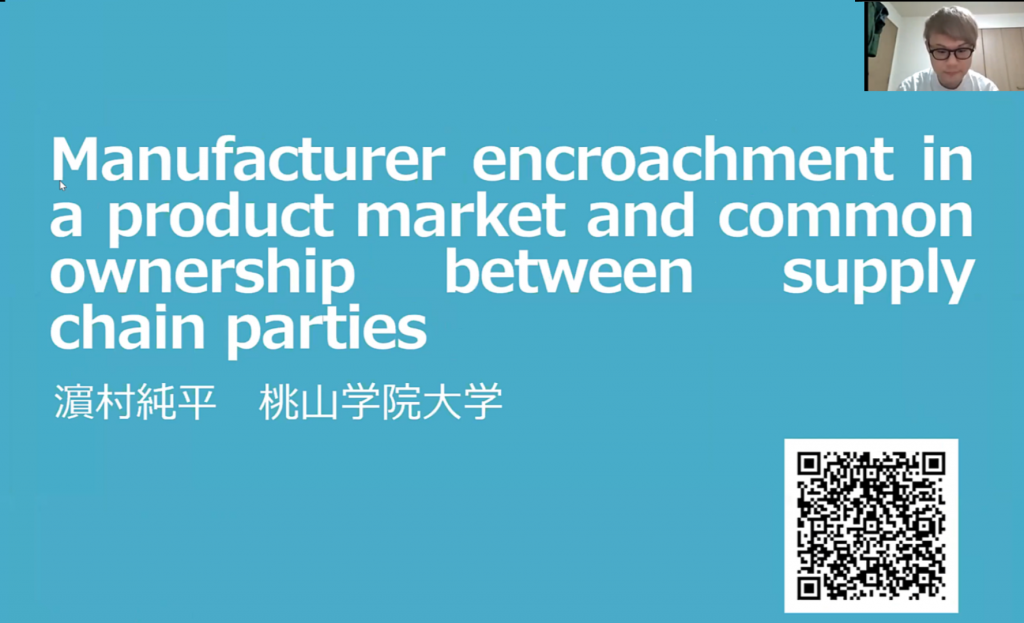日本管理会計学会 会員各位
日本管理会計学会第1回リサーチセミナーについて,下記のとおりのプログラムで開催することになりましたので,再度ご案内申し上げます。
感染症予防のための対面参加の定員(約80名)にご注意ください。もしも定員の超過があった場合は先着順とし,定員外の方はZOOMでの参加をお願い致します。ただし,ZOOMの中継については,低品質であったり中断の可能性がございます。
6月6日までに申込みをされた方には,論文ファイルなどをダウンロードできるドロップボックスのアドレスを6月11日までに順次,案内する予定です。もし,開催日の前日までに連絡がない場合,お手数ですが新井までご一報ください。6月7日以降の申込みの場合,案内が直前になる予定です。ご容赦ください。
なお,セミナー前日までに,関連資料はこちらのドロップボックスに順次アップロードされる予定です。感染症対策のため,紙資料の配布を控えるように大学側から指示されておりますので,こちらのデータを利用されますよう,ご注意ください。
記
開催日時:2022年6月18日(土)13時30分開始 17時00分終了
開催方法:対面
(ZOOMによる中継も予定。ただし,質疑などは対面が優先されます。また,中継は低品質であったり中断の可能性があります。)※1
場 所:大阪公立大学なかもずキャンパス(https://www.osakafu-u.ac.jp/info/campus/nakamozu/)
B1棟 第2講義室(予定)※2
※1 新型コロナの感染状況によっては,全面的にZOOMなどに移行する可能性があります。
※2 大阪公立大学は,2022年4月に大阪市立大学と大阪府立大学の合併により誕生する新大学です。
学会会場は,商学部がある旧大阪市立大学のキャンパスではなく,旧大阪府立大学のキャンパスです。
<概要>
【第1報告】13:35-14:20(報告時間20分,討論25分)
報告タイトル:予算参加が業績予想におよぼす影響
概要:本研究の目的は,企業内の予算管理実践,中でも多くの企業で採用されている予算参加が,企業外部者に向けて公表される業績予想にどのような影響を及ぼすかを解明することにある。データは日本の上場企業を対象とした郵送質問票調査とアーカイバルデータを活用している。分析の結果,(1)ミドルマネジャーの予算参加の程度が高いほど業績予想は悲観的になること,(2)従業員の金銭的報酬と企業業績の関係が強い企業ほど予算参加と業績予想の関係性が強まることなどを明らかにした。
氏名:岩澤佳太・石田惣平(東京理科大学経営学部・立教大学経済学部)
討論者:佐久間智広先生(神戸大学大学院経営学研究科)
【第2報告】14:30-15:15(報告時間20分,討論25分)
報告タイトル:中小企業における資本予算の採用―QDAによる中小企業へのインタビュー調査の分析―
概要:従来の大企業の資本予算を対象とした研究では,経済性評価技法やマネジメント・プロセスに着目し,採用要因やパフォーマンスへの影響が質問票調査によって検証されてきた。一方で,中小企業がどのようなマネジメント・プロセスを経て,投資を実行しているのかは,ほとんど調査されていない。そこで,本研究は中小企業の資本予算実務をインタビュー調査によって,記述することを目的とする。そして,インタビュー調査の結果について,質的データ分析(Qualitative Data Analysis)を実施し,中小企業における資本予算の採用の決定要因を探求する。
氏名:牧野功樹(拓殖大学商学部)
討論者:庵谷治男先生(東洋大学経営学部)
【チュートリアル・セミナー1】15:30-16:05
担当:井上謙仁先生(近畿大学経営学部),濵村純平先生(桃山学院大学経営学部)
セミナータイトル:管理会計研究における日経NEEDSデータの利用入門
概要:第1報告の岩澤・石田報告にあるように,近年,管理会計分野でも財務諸表データを利用した研究が増加している。本セミナーでは,これまで日経NEEDSデータを利用したことがない研究者へ向けて,
・質問票と財務諸表データを利用した論文の事例紹介
・日経NEEDSによるデータ取得の解説・実演
を行う。
【チュートリアル・セミナー2】16:15-16:50
担当:町田遼太先生(東京都立大学経済経営学部),荻原啓佑先生(早稲田大学商学学術院)
セミナータイトル:管理会計研究におけるインタビューデータのQDA入門
概要:第2報告の牧野報告にあるように,近年,管理会計分野でもインタビューデータをQDAソフトウェアにより分析するというアプローチが増加している。本セミナーでは,これまでQDAを利用したことがない研究者へ向けて,
・QDAを利用した論文の事例紹介
・Nvivoによるデータ取得の解説・実演
を行う。なお,Nvivoは14日間無料トライアルが可能なので,インストールしたPCを持参すると,より理解が深まるものと思われる。
参加申込:新井康平(旧所属:大阪府立大学経済学研究科,新所属:大阪公立大学商学部)
件名を「リサーチセミナー参加希望(対面 or ZOOM)」として,下記の内容をメール本文に記載の上,お申し込みください。
arai[at]omu.ac.jp,[at]を@に変更のこと。
(新井の旧大阪府立大学のアドレスは,近日中に連絡が出来なくなる予定ですので,使用しないでください。)
・お名前
・ご所属
・連絡先メールアドレス
・対面 or ZOOMでのどちらの参加希望か