 ■■ 日本管理会計学会2013年度第3回フォーラムが,第41回九州部会と兼ねて2013年11月16日土曜日に大分大学旦野原キャンパスにおいて開催された。今回のフォーラムでは,『大分・別府,九州から地域経済・地域産業の将来を考える』というテーマで,大分・別府,九州の地域産業に焦点を当てた企業講演と研究報告が行われた。大会準備委員長である大崎美泉氏(大分大学)の開会の挨拶があり,第1部では加藤典生(大分大学)の司会のもと,高橋幹氏(南九州税理士会大分県連合会副会長),桑野和泉氏(由布院玉の湯代表取締役社長)の2組が講演され,第2部では大下丈平氏(九州大学)の司会のもと,魚井和樹氏(ダイハツ九州株式会社取締役相談役),宮地晃輔氏(長崎県立大学)の2組から企業講演,研究報告が行われた。いずれの講演および報告もフロアから活発な質問や意見があり,有意義な議論がなされた。その後,場所を移して懇親会が行われ,散会となった。
■■ 日本管理会計学会2013年度第3回フォーラムが,第41回九州部会と兼ねて2013年11月16日土曜日に大分大学旦野原キャンパスにおいて開催された。今回のフォーラムでは,『大分・別府,九州から地域経済・地域産業の将来を考える』というテーマで,大分・別府,九州の地域産業に焦点を当てた企業講演と研究報告が行われた。大会準備委員長である大崎美泉氏(大分大学)の開会の挨拶があり,第1部では加藤典生(大分大学)の司会のもと,高橋幹氏(南九州税理士会大分県連合会副会長),桑野和泉氏(由布院玉の湯代表取締役社長)の2組が講演され,第2部では大下丈平氏(九州大学)の司会のもと,魚井和樹氏(ダイハツ九州株式会社取締役相談役),宮地晃輔氏(長崎県立大学)の2組から企業講演,研究報告が行われた。いずれの講演および報告もフロアから活発な質問や意見があり,有意義な議論がなされた。その後,場所を移して懇親会が行われ,散会となった。
■■ 第1報告:高橋 幹氏(南九州税理士会大分県連合会副会長)
「顧問先の経営成績から大分の景気動向をさぐる」
 高橋氏は,顧問先の法人データをもとに業種別に区分して経営分析を行い,その結果から大分県の企業の現状と課題を提示された。同分析結果から,法人税額が前年度比で見た場合,およそ半分が増えている一方で,残りの半分が減少傾向にあることが明らかとなり,これを受けて,大分では,良い会社とそうでない会社が明確になってきており,2極化してきていることが指摘された。また,同分析結果から,大分の土地という点でも,オリンピックの東京開催決定やアベノミクス効果の影響が入ってきていると判断され,具体的には建設業,不動産業,とりわけリフォームがそうした影響を受けていると述べられた。今後の課題として,消費税率の引き上げの問題,納税資産の問題,相続税の問題が今後の大分の中小企業にとってかなり厳しい対応が必要になってくると主張された。
高橋氏は,顧問先の法人データをもとに業種別に区分して経営分析を行い,その結果から大分県の企業の現状と課題を提示された。同分析結果から,法人税額が前年度比で見た場合,およそ半分が増えている一方で,残りの半分が減少傾向にあることが明らかとなり,これを受けて,大分では,良い会社とそうでない会社が明確になってきており,2極化してきていることが指摘された。また,同分析結果から,大分の土地という点でも,オリンピックの東京開催決定やアベノミクス効果の影響が入ってきていると判断され,具体的には建設業,不動産業,とりわけリフォームがそうした影響を受けていると述べられた。今後の課題として,消費税率の引き上げの問題,納税資産の問題,相続税の問題が今後の大分の中小企業にとってかなり厳しい対応が必要になってくると主張された。
■■ 第2報告:桑野和泉氏(由布院玉の湯代表取締役社長)
「由布院の観光・まちづくり」
 桑野氏は,まず大分県が大分駅を中心にしたまちづくりが行われていることを伝えた後に,日本の「観光」が世界的に見て遅れていることを指摘し,日本製品の販売を含めて海外の方々が日本に来てもらうことが大事であり,オリンピックが日本で開催されることが決まった今日にあって,今こそ日本の持っている力を最大限発揮するべきであると主張された。人口減少社会が我々の想定以上の速さで進む中,定住人口が望めなければ交流人口を向上させていく必要があるとされ,各業種の経済効果を期待できる観光の重要性が指摘され,由布院の観光の取組が紹介された。由布院では,調和をモットーに,宿泊施設の価格帯に幅を持たせることで,競争ではなく共存関係を築けていること,女性のリピーターの方が多いこと,温泉街を作らず小規模な温泉地を意識していること,馬車が通ることでゆっくりな町であることをアピールしていること,世代交代を早めることで自らの判断に責任を持ってもらうにようにしていることなどの取組が示された。また,数字から見えない観光は議論できないとし,会計数値の重要性も指摘された。
桑野氏は,まず大分県が大分駅を中心にしたまちづくりが行われていることを伝えた後に,日本の「観光」が世界的に見て遅れていることを指摘し,日本製品の販売を含めて海外の方々が日本に来てもらうことが大事であり,オリンピックが日本で開催されることが決まった今日にあって,今こそ日本の持っている力を最大限発揮するべきであると主張された。人口減少社会が我々の想定以上の速さで進む中,定住人口が望めなければ交流人口を向上させていく必要があるとされ,各業種の経済効果を期待できる観光の重要性が指摘され,由布院の観光の取組が紹介された。由布院では,調和をモットーに,宿泊施設の価格帯に幅を持たせることで,競争ではなく共存関係を築けていること,女性のリピーターの方が多いこと,温泉街を作らず小規模な温泉地を意識していること,馬車が通ることでゆっくりな町であることをアピールしていること,世代交代を早めることで自らの判断に責任を持ってもらうにようにしていることなどの取組が示された。また,数字から見えない観光は議論できないとし,会計数値の重要性も指摘された。
■■第3報告:魚井和樹氏(ダイハツ九州株式会社取締役相談役)
「ダイハツ九州のめざすところ」
 魚井氏は,グローバル化に着目しながら,ダイハツ九州の今後の方向性について報告された。同社では,世界一のスモールカーを目指すために,軽自動車に相応しい自動化,設備のシンプル化に力を入れ,工場設置に対する工期短縮に取り組まれていることが説明された。海外との競争において,販売価格を上げることが困難な状況では原価低減活動が重要であり,そのために現地(大分・九州地域)調達率の向上を目指すとともに,原単位を下げていくこと,スピード力,一人で何でもできる能力,診える化が必要であることが主張された。時間とお金がかかっていてはグローバル化の時代に海外で勝負にならないことが繰り返し指摘された。
魚井氏は,グローバル化に着目しながら,ダイハツ九州の今後の方向性について報告された。同社では,世界一のスモールカーを目指すために,軽自動車に相応しい自動化,設備のシンプル化に力を入れ,工場設置に対する工期短縮に取り組まれていることが説明された。海外との競争において,販売価格を上げることが困難な状況では原価低減活動が重要であり,そのために現地(大分・九州地域)調達率の向上を目指すとともに,原単位を下げていくこと,スピード力,一人で何でもできる能力,診える化が必要であることが主張された。時間とお金がかかっていてはグローバル化の時代に海外で勝負にならないことが繰り返し指摘された。
■■第4報告:宮地晃輔氏(長崎県立大学)
「A社造船所における新造船事業の採算性改善のための方策(2)」
 宮地氏は,リーマンショック以降,船会社の需要低下を原因とした「極端な買い手市場」による造船市場の競争激化の状況のもとで,造船準大手のA社造船所で取組が本格化した原価企画の現状と問題点を報告し,それを踏まえて採算性改善の方策について提示された。ここでは,A社が原価企画からの効果を当初期待した通りには得られていないこと,また,これまでの地元の協力先企業との関係で新たなサプライヤー(特に海外)を参入させることが困難であるといった,保守的なサプライヤーの存在が採算性の改善を阻害していることが,新造船事業の採算性改善のための課題であったことを指摘し,同社や協力先企業も新規参入への抵抗が強いことから,保守的なサプライチェーンを前提とした採算性改善の方策として,これまで不足していた両者の協力関係を強化していくことが提示された。
宮地氏は,リーマンショック以降,船会社の需要低下を原因とした「極端な買い手市場」による造船市場の競争激化の状況のもとで,造船準大手のA社造船所で取組が本格化した原価企画の現状と問題点を報告し,それを踏まえて採算性改善の方策について提示された。ここでは,A社が原価企画からの効果を当初期待した通りには得られていないこと,また,これまでの地元の協力先企業との関係で新たなサプライヤー(特に海外)を参入させることが困難であるといった,保守的なサプライヤーの存在が採算性の改善を阻害していることが,新造船事業の採算性改善のための課題であったことを指摘し,同社や協力先企業も新規参入への抵抗が強いことから,保守的なサプライチェーンを前提とした採算性改善の方策として,これまで不足していた両者の協力関係を強化していくことが提示された。
加藤典生(大分大学)


 ■■ 日本管理会計学会2013年度第2回フォーラムが,2013年7月13日土曜日に法政大学市ヶ谷キャンパスにおいて開催された。今回のフォーラムでは、統一論題の設定をしないで、すべて自由論題にてご報告いただく形式を採った。大会準備委員会委員長である福多裕志先生(法政大学)の開会の挨拶の後、福田淳児先生(法政大学)の総合司会の下で約3時間にわたって4名の先生方による意欲的な研究報告が行われ、活発な議論が展開された。その後、法政大学富士見坂校舎地下1階「カフェテリア」において、懇親会が開催された。各先生方の報告の概要は以下のとおりである。
■■ 日本管理会計学会2013年度第2回フォーラムが,2013年7月13日土曜日に法政大学市ヶ谷キャンパスにおいて開催された。今回のフォーラムでは、統一論題の設定をしないで、すべて自由論題にてご報告いただく形式を採った。大会準備委員会委員長である福多裕志先生(法政大学)の開会の挨拶の後、福田淳児先生(法政大学)の総合司会の下で約3時間にわたって4名の先生方による意欲的な研究報告が行われ、活発な議論が展開された。その後、法政大学富士見坂校舎地下1階「カフェテリア」において、懇親会が開催された。各先生方の報告の概要は以下のとおりである。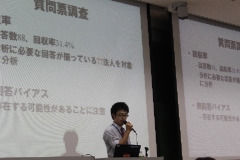 介護事業において、組織の公益志向(利益最大化以外の目的をもつ)が高い場合、それらが業績評価にどのように影響しているのかについて、千葉県で介護施設を運営する法人を対象とした調査の結果が報告された。報告では2つの仮説が示され、アンケート調査に基づく分析と考察が示された。第1の仮説は、組織の公益志向が強いほど使命達成測定尺度(利益以外の業績測定尺度)の利用度が高まるというものであり、これについては一部の使命達成尺度に対してしか影響は見られず、その影響も限定的であることが明らかにされた。また、規範的に示されてきた一般的見解とは差異が認められることも指摘された。第2の仮説は、組織の公益志向が高いほど、財務的業績尺度の重視度が低下するというものであった。これについては、先行研究と同様に公益志向が高いほど会計的コントロールを軽視していることが裏付けられた。
介護事業において、組織の公益志向(利益最大化以外の目的をもつ)が高い場合、それらが業績評価にどのように影響しているのかについて、千葉県で介護施設を運営する法人を対象とした調査の結果が報告された。報告では2つの仮説が示され、アンケート調査に基づく分析と考察が示された。第1の仮説は、組織の公益志向が強いほど使命達成測定尺度(利益以外の業績測定尺度)の利用度が高まるというものであり、これについては一部の使命達成尺度に対してしか影響は見られず、その影響も限定的であることが明らかにされた。また、規範的に示されてきた一般的見解とは差異が認められることも指摘された。第2の仮説は、組織の公益志向が高いほど、財務的業績尺度の重視度が低下するというものであった。これについては、先行研究と同様に公益志向が高いほど会計的コントロールを軽視していることが裏付けられた。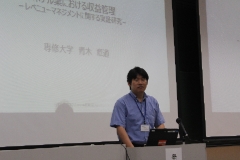 まず、レベニューマネジメントの定義および成果尺度について説明があり、本研究は、キャパシティに制約があるサービス産業を前提としていること、短期的な収益最大化を目的とした管理手法であること、そのため経営構造の変革を前提としていないこと、コストには言及しないことなどが示された。次に、ホテル業を対象として、どのような事業環境および収益管理の下であれば、レベニューマネジメントの短期的な財務尺度(成果尺度)を向上させることに繋がるのかについて検討がなされた。報告では、事業環境、収益管理に関する変数について因子分析、信頼性分析が示され、因子得点を説明変数とし、短期的な財務尺度および顧客関連尺度を被説明変数とした多重回帰分析が行われた。その結果、繁忙期と閑散期では財務尺度の向上に繋がる要因が異なることが明らかにされた。また、顧客関連尺度については、特にレベニューマネジメント導入環境の整備状況、販売価格コントロールの程度から影響を受けることが指摘された。
まず、レベニューマネジメントの定義および成果尺度について説明があり、本研究は、キャパシティに制約があるサービス産業を前提としていること、短期的な収益最大化を目的とした管理手法であること、そのため経営構造の変革を前提としていないこと、コストには言及しないことなどが示された。次に、ホテル業を対象として、どのような事業環境および収益管理の下であれば、レベニューマネジメントの短期的な財務尺度(成果尺度)を向上させることに繋がるのかについて検討がなされた。報告では、事業環境、収益管理に関する変数について因子分析、信頼性分析が示され、因子得点を説明変数とし、短期的な財務尺度および顧客関連尺度を被説明変数とした多重回帰分析が行われた。その結果、繁忙期と閑散期では財務尺度の向上に繋がる要因が異なることが明らかにされた。また、顧客関連尺度については、特にレベニューマネジメント導入環境の整備状況、販売価格コントロールの程度から影響を受けることが指摘された。 サービス業においてアメーバ経営がどのように導入され機能しているのか、レストラン運営会社の事例を例にとって報告された。まず、製造業で生成・発展してきたアメーバ経営とはいかなるものか、その特徴である時間当り採算およびフィロソフィーの概念について先行研究を取り上げながら詳細な説明がなされた。時間当り採算は、会計的な利益意識を強く持たせる役割があるが、一方で部分最適に陥る危険性があるので、その欠点を補う形でフィロソフィーを浸透させていくと適切な形でアメーバ経営が機能することが説明された。報告では、レストランを運営している「株式会社ぶどうの木」におけるアメーバ経営の事例が紹介され、時間当り採算とフィロソフィーのパッケージが、当該レストランにおけるフロントラインの高効率および高効果を両立させるよう機能していることが示された。
サービス業においてアメーバ経営がどのように導入され機能しているのか、レストラン運営会社の事例を例にとって報告された。まず、製造業で生成・発展してきたアメーバ経営とはいかなるものか、その特徴である時間当り採算およびフィロソフィーの概念について先行研究を取り上げながら詳細な説明がなされた。時間当り採算は、会計的な利益意識を強く持たせる役割があるが、一方で部分最適に陥る危険性があるので、その欠点を補う形でフィロソフィーを浸透させていくと適切な形でアメーバ経営が機能することが説明された。報告では、レストランを運営している「株式会社ぶどうの木」におけるアメーバ経営の事例が紹介され、時間当り採算とフィロソフィーのパッケージが、当該レストランにおけるフロントラインの高効率および高効果を両立させるよう機能していることが示された。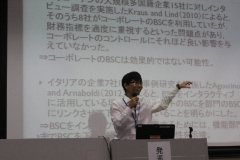 戦略的業績評価システムは機能部門において効果的であるのか、それはキャプランとノートンが主張するバランスト・スコアカードの仕組みと同じであるのか、という研究課題について、文献レビュー及び事例研究の経過が報告された。文献レビューでは、一般的なバランスト・スコアカードの仕組みについて解説がなされた後、とくにマーケティング部門で行われている戦略的業績評価システムの概要について検討がなされた。次に事例研究では、現在、報告者が進めているバランスト・スコアカードに関する調査の途中経過について説明があった。これらの考察に基づいて、1. 機能部門では、因果関係を伝達する仕組みとして戦略マップは効果的ではないのではないか、また、2. 機能部門では、相対評価で報酬とリンクしている戦略的業績評価システムが効果的であるのではないか、という2つの新たな仮説が提示された。
戦略的業績評価システムは機能部門において効果的であるのか、それはキャプランとノートンが主張するバランスト・スコアカードの仕組みと同じであるのか、という研究課題について、文献レビュー及び事例研究の経過が報告された。文献レビューでは、一般的なバランスト・スコアカードの仕組みについて解説がなされた後、とくにマーケティング部門で行われている戦略的業績評価システムの概要について検討がなされた。次に事例研究では、現在、報告者が進めているバランスト・スコアカードに関する調査の途中経過について説明があった。これらの考察に基づいて、1. 機能部門では、因果関係を伝達する仕組みとして戦略マップは効果的ではないのではないか、また、2. 機能部門では、相対評価で報酬とリンクしている戦略的業績評価システムが効果的であるのではないか、という2つの新たな仮説が提示された。