2019年6月29日(土)
追手門学院大学 井上 秀一
2019年度第1回リサーチセミナーは,2019年6月29日(土)13:00~17:40に青山学院大学(青山キャンパス16号館2階)16201教室において,開催されました。当日の参加者は30名程度であり,日本管理会計学会会長の水野一郎氏(関西大学)より開会の挨拶が,日本管理会計学会副会長の澤邉紀生氏(京都大学)より全体講評がありました。山口直也氏(青山学院大学)の司会によりリサーチセミナーが進められ,海老原佑氏(東京理科大学大学院生),庄司豊氏(京都大学大学院生),梅田充氏(専修大学)の研究報告に対して,フロアから有益なコメント,質問が多くあり,活発な議論が行われました。
 第1報告 海老原佑氏(東京理科大学大学院修士課程)
第1報告 海老原佑氏(東京理科大学大学院修士課程)
報告論題「不正会計が株価に与える影響―金融庁課徴金制度からの考察―」
第1報告の海老原氏は,金融庁課徴金制度により,(1)株主は不正会計企業の判断を変えるのか,(2)株主は課徴金額をどのように判断するのか,(3)浮動株主は判断をどのように変えるのかという問題意識から,以下の仮説を立てています。
仮説1:金融庁課徴金納付命令の審査手続開始の決定により,株価に正の影響が現れる。
仮説2:より額の大きい課徴金は金融庁課徴金納付命令の審査手続開始の決定日後の株価に負の影響を与える。
仮説3:高い浮動株率は金融庁課徴金納付命令の審査手続開始の決定日後の株価に負の影響を与える。
これらの仮説に対し,海老原氏は,イベントスタディによる検証を行い,その結果,仮説1と仮説2は支持されたが,仮説3は支持されなかったことを報告しました。
 ディスカッサント:小倉昇氏(青山学院大学)
ディスカッサント:小倉昇氏(青山学院大学)
海老原氏の報告に対し,ディスカッサントの小倉氏は,修士論文としては広範な範囲を網羅しようとしているので,焦点を絞った方がよいのではないかと指摘した後,以下の3点についてコメントしました。
(1)イベントウィンドの決定は重要であり,試行錯誤的に,研究目的に適合した観察範囲を選択すべきである。
(2) CARの有意性は統計値で示す。
(3) 付随情報(先行情報・同時発表情報・後発情報)の影響を分析モデルに組み込むことが,イベントの株価への効果を明確にする。
 第2報告 庄司豊氏(京都大学大学院博士後期課程)
第2報告 庄司豊氏(京都大学大学院博士後期課程)
報告論題「制度的複雑性の下での管理会計変化」
第2報告の庄司氏は,複数の制度ロジックが存在する状況において,どのような管理会計変化のパターンが生じるのかという問題意識から,Besharov and Smith(2014)をフレームワークとして先行研究のレビューを行っています。
庄司氏は,制度的複雑性下での管理会計変化のパターンとして,(1)競合状態,(2)支配状態,(3)乖離状態という3つが存在し,制度的複雑性の状態によって管理会計変化のパターンが異なることを報告しています。加えて,庄司氏は,先行研究では,一部の制度的複雑性の状態における管理会計変化しか取り扱われていないことを指摘しました。
 ディスカッサント:庵谷治男氏(東洋大学)
ディスカッサント:庵谷治男氏(東洋大学)
庄司氏の報告に対し,ディスカッサントの庵谷氏は,一様ではない管理会計の変化を捉えようとする挑戦的な研究と指摘したうえで,以下の点で課題があるとコメントしました。
(1) 管理会計研究としての貢献
庄司氏の研究は,Besharov and Smith(2014)のフレームワークにもとづいて管理会計変化を類型化(パターン化)していることに貢献のひとつを見出しているが,類型化することが管理会計研究へどのようなインプリケーションをもたらすのか,より一歩進めた考察があった方が,貢献が鮮明となるのではないか。
(2) 分析フレームワーク
Besharov and Smith(2014)のフレームワークの説明について,本文ならびに図表で読者にとってわかりやすい説明,とくに縦軸(中心性)は中心となる制度ロジックの数(複数or単一)を,横軸(適合性)は制度ロジックと行為との適合度合いを表している点を説明に加える必要がある。
(3) 研究方法
レビュー論文の抽出方法と対象論文の分析方法について,具体的にどのような手順によって実施されたのか説明が必要。いわゆる再現可能性についてどのような配慮がなされているのか言及することが望ましい。
(4) 分析結果
分析結果について,統一の記述形式をとるか図表等でまとめを載せる方が,筆者の分類の意図が伝わるのではないか。分離化,ハイブリッド実践化,形骸化,選択的例示化,制度化という5つの概念の説明と事例との関係性をより丁寧に説明してほしい。
 第3報告 梅田充氏(専修大学)
第3報告 梅田充氏(専修大学)
報告論題「インタンジブルズ・マネジメントの統合化―コミュニケーション,戦略管理,価値創造―」
第3報告の梅田氏は,インタンジブルズ・マネジメントの統合化をテーマに先行研究の整理を行い,コミュニケーション,戦略管理,価値創造の統合化を扱った研究が不足していることを指摘しています。そのうえで,統合化における3つの論点として,統合思考,コネクティビティ,マテリアリティを提示しています。
梅田氏は,統合化を図る手段としてバランスト・スコア・カード(BSC)に着目し,コミュニケーション,戦略管理,価値創造を行っている情報・通信業のA社に対し,インタビュー調査を実施しています。梅田氏は,インタビュー調査の結果,BSCを用いることで,インタンジブルズ・マネジメントの統合化が可能となることを指摘し,統合化の効果として,次の3つをあげています。
① ステークホルダーの理解を深めコミュニケーションを促進する
② 戦略に基づく組織間アラインメントの確立
③ 企業価値を高める価値創造と価値毀損の両面からの価値創造
 ディスカッサント:内山哲彦氏(千葉大学)
ディスカッサント:内山哲彦氏(千葉大学)
梅田氏の報告に対し,ディスカッサントの内山氏は,(1)インタンジブルズ・マネジメントの統合化におけるBSC,とくに戦略マップの有用性を明らかにしたこと,(2)統合化によって統合思考,コネクティビティ,マテリアリティが担保されることを明らかにしたこと,(3)統合化による効果を明らかにしたこと,という3点を本研究の貢献として指摘しています。そのうえで,内山氏は,以下の点について課題があるとコメントしました。
① 検討したい問題は測定なのか,マネジメントなのか,両方なのか。また,両者にはどのような関係があるのか。
② インタンジブル・マネジメントの統合化においては,具体的に何を統合化し,なぜ統合化が必要なのか。
③ 統合思考,コネクティビティ,マテリアリティはなぜ論点となるのか。
④ 本研究においてケース・スタディはどのような位置づけなのか。
⑤ 統合化に期待される効果はどのような検討から導かれるものなのか。

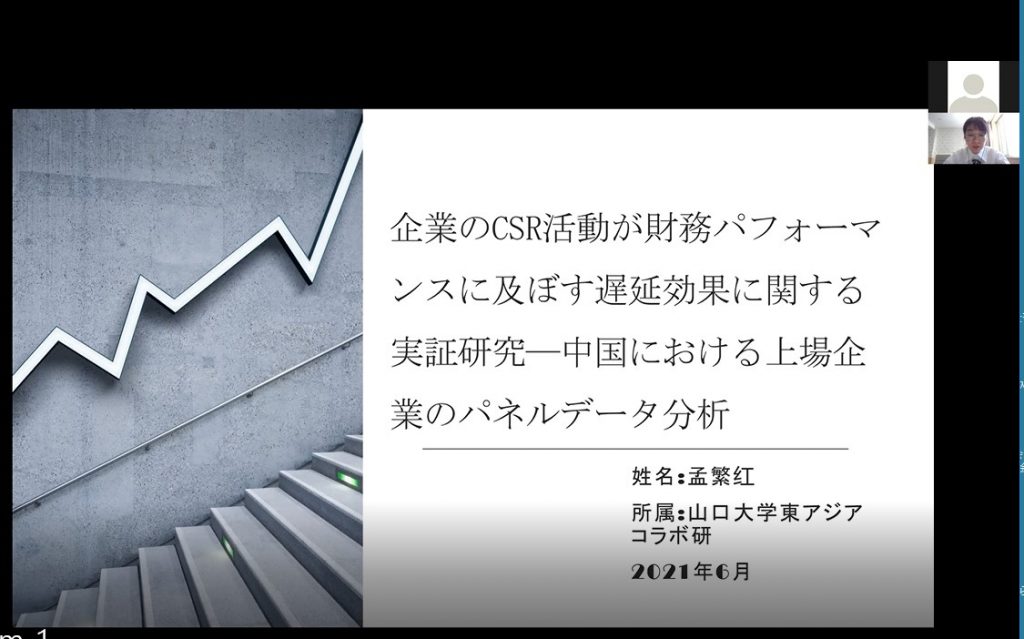

 なお,リサーチセミナーは例年6-7月に1回,10-11月に1回の開催を予定していますが,2020年度は新型コロナウィルスの感染拡大を受けて,第1回は中止となりました。このため,2020年度は第2回のみとなりました。
なお,リサーチセミナーは例年6-7月に1回,10-11月に1回の開催を予定していますが,2020年度は新型コロナウィルスの感染拡大を受けて,第1回は中止となりました。このため,2020年度は第2回のみとなりました。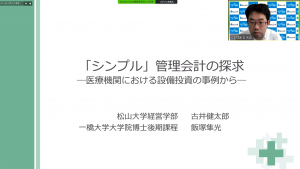 そして,このように必ずしも洗練された意思決定を⾏なっているとは⾔えない医療機関の事例に基づき,洗練された投資意思決定について理解し活⽤できるようになるためのコストを⽀払うことよりも,理論的とは言い難いが簡単に理解・算出できる経済性評価と管理会計以外の要素を組み合わせる「シンプル」な管理会計が有用であることを主張しています。そして,このような「シンプル」管理会計の運⽤から,投資意思決定に有⽤な豊かな情報を得るとともに,医療機関での管理会計の普及やマネジメントに対する意識向上を⽬指していることを指摘しています。
そして,このように必ずしも洗練された意思決定を⾏なっているとは⾔えない医療機関の事例に基づき,洗練された投資意思決定について理解し活⽤できるようになるためのコストを⽀払うことよりも,理論的とは言い難いが簡単に理解・算出できる経済性評価と管理会計以外の要素を組み合わせる「シンプル」な管理会計が有用であることを主張しています。そして,このような「シンプル」管理会計の運⽤から,投資意思決定に有⽤な豊かな情報を得るとともに,医療機関での管理会計の普及やマネジメントに対する意識向上を⽬指していることを指摘しています。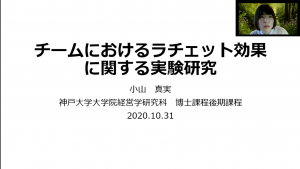 本研究の主たる結果としては,第1にチームにおいては,ラチェット効果のメカニズムが異なることを理論と実験の双方から示したことにあり,チームとして働く従業員の不平等回避が強い場合,経営者が特別なことをせずとも,ラチェット効果が生じないことを明らかにしていると指摘しています。また第2に,熟練者と未熟練者がチームを組むときに,未熟練者の能力が伸びる効果と熟練者が手を抜くことを抑制する効果があることを示しています。このことは,従業員の教育研修制度に関する研究・実務に新たな知見を提示しています。
本研究の主たる結果としては,第1にチームにおいては,ラチェット効果のメカニズムが異なることを理論と実験の双方から示したことにあり,チームとして働く従業員の不平等回避が強い場合,経営者が特別なことをせずとも,ラチェット効果が生じないことを明らかにしていると指摘しています。また第2に,熟練者と未熟練者がチームを組むときに,未熟練者の能力が伸びる効果と熟練者が手を抜くことを抑制する効果があることを示しています。このことは,従業員の教育研修制度に関する研究・実務に新たな知見を提示しています。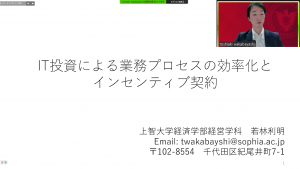 本研究の主たる結論として,第1にITリテラシーがある閾値より大きいのであれば最適なRPA等の導入水準が決まり,そのもとでの報酬契約が提示されるから,RPA等の導入と業績評価システムを統合的に,かつ業務や事業特性に応じて考えるべきであることを指摘しています。また,第2に人工知能(AI)とRPAには相補性があること,第3にITリテラシーが高いほど,組織内のIT教育は有意義であることを主張しています。また第4に本部の方がエイジェント(事業部)よりもITリテラシーが低かったとしても,RPA等の導入の決定権を本部が留保した方が良いケースが存在し,その傾向は事業リスクが高いほど高まることを指摘しています。
本研究の主たる結論として,第1にITリテラシーがある閾値より大きいのであれば最適なRPA等の導入水準が決まり,そのもとでの報酬契約が提示されるから,RPA等の導入と業績評価システムを統合的に,かつ業務や事業特性に応じて考えるべきであることを指摘しています。また,第2に人工知能(AI)とRPAには相補性があること,第3にITリテラシーが高いほど,組織内のIT教育は有意義であることを主張しています。また第4に本部の方がエイジェント(事業部)よりもITリテラシーが低かったとしても,RPA等の導入の決定権を本部が留保した方が良いケースが存在し,その傾向は事業リスクが高いほど高まることを指摘しています。 第1報告 海老原佑氏(東京理科大学大学院修士課程)
第1報告 海老原佑氏(東京理科大学大学院修士課程) ディスカッサント:小倉昇氏(青山学院大学)
ディスカッサント:小倉昇氏(青山学院大学) 第2報告 庄司豊氏(京都大学大学院博士後期課程)
第2報告 庄司豊氏(京都大学大学院博士後期課程) ディスカッサント:庵谷治男氏(東洋大学)
ディスカッサント:庵谷治男氏(東洋大学) 第3報告 梅田充氏(専修大学)
第3報告 梅田充氏(専修大学) ディスカッサント:内山哲彦氏(千葉大学)
ディスカッサント:内山哲彦氏(千葉大学)