■■2016年度第1回関西・中部部会が、5月21日(土)に大阪経済大学にて13:10より開催された(準備委員長:三浦徹志(大阪経済大学),準備委員:浅田拓史(同))。関東からの学会員諸氏、実務家の方々の参加をいただいた(院生・学生を含め出席者34名)。3つの自由論題報告と企業講演を行い、いずれも活発な質疑応答があった。
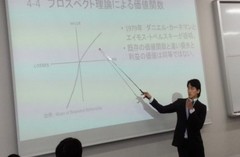 ■第1報告は,岡田朋之氏(関西大学会計専門職大学院生)による、「企業価値評価法の一考察―行動ファイナンスから考える意思決定―(試論)」。一般的な企業価値形成・事業価値評価技法とその基礎となっているCAPM(「資本資産(株式・債権)の評価モデル」)を元にした思考に対して、経営判断・投資行動に内在する(可能性のある)アノマリ―(変則性)の体系(行動ファイナンス)に着目して考察が加えられた。伝統的市場観では価格機構によってノイズは市場で合理的に調整されると仮定されているが、現実の経営において資本コストを上回るキャッシュフローをあげようとする企業価値経営観では、リスク予測、市場予測(β)とリスクプレミアム、キャッシュインフローをベースに具体的な事業の現在価値評価を行う。将来業績予測に際しては、不確実性が含まれた独自の経営判断でプレミアムを認識する。非財務情報、情報の非対称性、プリンシパル・エージェント問題等を前提として価格付けが行われるのである。現実の経営意思決定は過去業績延長の判断の上に意思的、創造的な戦略的行動が行われる。
■第1報告は,岡田朋之氏(関西大学会計専門職大学院生)による、「企業価値評価法の一考察―行動ファイナンスから考える意思決定―(試論)」。一般的な企業価値形成・事業価値評価技法とその基礎となっているCAPM(「資本資産(株式・債権)の評価モデル」)を元にした思考に対して、経営判断・投資行動に内在する(可能性のある)アノマリ―(変則性)の体系(行動ファイナンス)に着目して考察が加えられた。伝統的市場観では価格機構によってノイズは市場で合理的に調整されると仮定されているが、現実の経営において資本コストを上回るキャッシュフローをあげようとする企業価値経営観では、リスク予測、市場予測(β)とリスクプレミアム、キャッシュインフローをベースに具体的な事業の現在価値評価を行う。将来業績予測に際しては、不確実性が含まれた独自の経営判断でプレミアムを認識する。非財務情報、情報の非対称性、プリンシパル・エージェント問題等を前提として価格付けが行われるのである。現実の経営意思決定は過去業績延長の判断の上に意思的、創造的な戦略的行動が行われる。
シャープやトヨタなど著名な事例考察により、シナリオ分析等で加味すべき問題としてプロスペクト理論、サンクコスト効果、心の保守性、ギャンブラーのジレンマなど行動心理学の知見による政策判断の特性、偏り(歪み)の見極めの重要性が検討された。
■第2報告は,井上秀一氏(追手門学院 大学 経営学部)による「医療機関の管理会計システムとミドルマネジメント―ある地域の中核医療機関を対象とした事例研究―」。医療機関の管理会計システムにおけるミドルマネジメントの機能の重要性に注目し、ミドルマネジメントはどのような役割を、どのようにして果たしているのかについて詳細な検討、分析が行われた。本研究では,医療専門職のミドルマネジメント(例えば診療科部長や看護師長等)がトップとロワーの間でどのように組織内の調整を行っているのかについて焦点が当てられている。先行研究で,医療機関の管理会計システムにおけるミドルマネジメントの役割として,トップから現場への会計的な影響を吸収する「吸収役」,あるいはトッ プと現場の橋渡しを行う「双方向の窓」という 2 つの役割があることが指摘されていることを受けて,医療機関への参与観察をはじめとする精緻なリサーチデザインによるエスノグラフィックなアプローチを採用し,ミドルマネジメントがどのようにして「吸収役」あるいは「双方向の窓」としての役割を果たしながら組織内を調整しているのか,そのプロセスを明らかにした。医療機関の組織的特徴として、専門知識によるアイデンティティが強くこれに基づく専門職集団が形成されることが一般的にみられる。そこでは、効率性・採算性を求める管理会計システムはコンフリクトを生みやすく、また専門職活動は外部の規範がはたらき、医療機関としての目標と専門職集団の目標を一致させることの困難さが指摘されてきた。この、トップが関与できない活動が多くある現実に対して、管理会計のシステムの導入とその運用にミドルマネジメントが果たす役割の重要性と期待が大きいことが首肯される。
大学 経営学部)による「医療機関の管理会計システムとミドルマネジメント―ある地域の中核医療機関を対象とした事例研究―」。医療機関の管理会計システムにおけるミドルマネジメントの機能の重要性に注目し、ミドルマネジメントはどのような役割を、どのようにして果たしているのかについて詳細な検討、分析が行われた。本研究では,医療専門職のミドルマネジメント(例えば診療科部長や看護師長等)がトップとロワーの間でどのように組織内の調整を行っているのかについて焦点が当てられている。先行研究で,医療機関の管理会計システムにおけるミドルマネジメントの役割として,トップから現場への会計的な影響を吸収する「吸収役」,あるいはトッ プと現場の橋渡しを行う「双方向の窓」という 2 つの役割があることが指摘されていることを受けて,医療機関への参与観察をはじめとする精緻なリサーチデザインによるエスノグラフィックなアプローチを採用し,ミドルマネジメントがどのようにして「吸収役」あるいは「双方向の窓」としての役割を果たしながら組織内を調整しているのか,そのプロセスを明らかにした。医療機関の組織的特徴として、専門知識によるアイデンティティが強くこれに基づく専門職集団が形成されることが一般的にみられる。そこでは、効率性・採算性を求める管理会計システムはコンフリクトを生みやすく、また専門職活動は外部の規範がはたらき、医療機関としての目標と専門職集団の目標を一致させることの困難さが指摘されてきた。この、トップが関与できない活動が多くある現実に対して、管理会計のシステムの導入とその運用にミドルマネジメントが果たす役割の重要性と期待が大きいことが首肯される。
■第3報告は、和田淳蔵氏(岡山大学)による「利 益管理論―史的分析を踏まえて―」である。 本報告では,『管理・コントロール』の現代的解釈を管理会計の史的過程から探索している。当該『管理』問題を、歴代研究を踏まえ労務管理にはじまる「原価管理」と、財務管理に由来する「利益管理」の系譜に分け、それぞれが付託された機能を考察した上で、両者が管理会計として融合・統合される史的展開を解明。原価計算の要求事由と利益計算のそれが標準化問題を通じて会計的特質を備えた事情を明らかにし、標準原価計算の損益計算への全面適応として予算管理の制度的成立に着目し、この契機を1920年?1930年代末葉の米国における間接費、固定費の管理問題の検討によって詳らかにする。
益管理論―史的分析を踏まえて―」である。 本報告では,『管理・コントロール』の現代的解釈を管理会計の史的過程から探索している。当該『管理』問題を、歴代研究を踏まえ労務管理にはじまる「原価管理」と、財務管理に由来する「利益管理」の系譜に分け、それぞれが付託された機能を考察した上で、両者が管理会計として融合・統合される史的展開を解明。原価計算の要求事由と利益計算のそれが標準化問題を通じて会計的特質を備えた事情を明らかにし、標準原価計算の損益計算への全面適応として予算管理の制度的成立に着目し、この契機を1920年?1930年代末葉の米国における間接費、固定費の管理問題の検討によって詳らかにする。
課題として、標準原価および標準原価計算、予算管理、直接原価計算、投資利益率管理、損益分岐点分析、さらに近年の原価企画、ABC、BSC等の技法を通底する論理の探索を視野に、管理会計の機能的側面である利益管理論の歴史的経緯を探り、副材として標準原価計算を現代管理会計の源流とみて標準原価と予算統制の史的発展過程に焦点を当てる。両者に関連する操業度問題、間接費管理および変動費予算等が考察され、原価管理が科学的管理に端を発する課業管理・生産管理の系譜を引き、予算管理・財務管理機能は会計の本来的属性として損益計算システムにより収益・費用・利益の標準化へと結実した点が示唆される。
論究の里標に標準原価計算の制度的定立者としてG.C.ハリソンの論考を再評価し、利益(予算)管理主導の趣旨を見い出し、管理会計史の観点からの意義を強調する。ハリソン標準原価論により、実は標準原価の計算制度(原価管理機能)としての完成が同時に利益の標準化(予算制度)を招来し、一方、利益の標準化への手法の制度化と差異分析の整備によって原価管理機能を果たす情報属性の役割は後退して、組織的業績管理・評価と責任会計のあり方へ焦点が移る。製造間接費の標準化過程で固定費、変動費の分離、操業度水準変動による原価差異額の賦課対象(操業度問題;生産主体から販売主体時代への移行)、不働費の期間損益計算による解消、管理可能費・不能費の認識など、すでに原価の標準化対象である製造領域の管理機能を超えて、関心は資本効率の問題としての利益の標準化、利益管理論へと向かいつつあったことが論述された。
■企業講演は,井上誠氏((株 )中村超硬代表取締役社長)による「先進的な製品応用技術(デバイス・テクノロジ)開発と経営戦略・業績管理―2015IPO―」であった。講演では,大阪府作成の有望企業紹介・プロモーションビデオを上映のうえ,1954操業、1964創設の会社概要および超硬合金の切断加工技術を基礎とした半世紀にわたる特色ある部品製作、実装装置・機器開発と積極的経営展開の歴史を紹介いただいた。
)中村超硬代表取締役社長)による「先進的な製品応用技術(デバイス・テクノロジ)開発と経営戦略・業績管理―2015IPO―」であった。講演では,大阪府作成の有望企業紹介・プロモーションビデオを上映のうえ,1954操業、1964創設の会社概要および超硬合金の切断加工技術を基礎とした半世紀にわたる特色ある部品製作、実装装置・機器開発と積極的経営展開の歴史を紹介いただいた。
ソニーの技術者出身の中村社長が率いる同社デバイス・テクノロジ開発は、耐摩耗部品事業、超精密研磨による内径測定用ゲージ製作、焼結ダイアモンド加工技術による素材提案、微小ダイアモンド部品を真空吸着し基板に配列させる電子部品吸着ノズルの量産、ダイアモンド粒を加工したワイヤーによるソーラー部品・太陽電池用ウエハーの世界最速切断(スライス)事業、さらに極小ノズルのノウハウを用いた医療機器製造など、シーズとコア技術を川下ニーズに丁寧に応用し横展開していく積極的かつ堅実な営業戦略が推進されていることが了解される。同時に長期にわたってデジタル化の波や景気変動を乗り越えられる「泥臭い事業の嗅覚とチャレンジ精神の重要性」を旨とする経営姿勢、社内の「自由闊達な人材育成方針」、昨年度IPOを成功させ高い評価を得るなどの「積極的な資本政策」等、技術・経営両面の経営努力について熱のこもったお話を伺うことができた。
大阪経済大学 三浦徹志


