■■日時・場所
●日 時 : 2012年5月26日(土)
●場 所 : 中部大学 春日井キャンパス 22号館2215講義室
■■日本管理会計学会2012年度第1回関西・中部部会が,2012年5月26日(土)に中部大学(愛知県春日井市)にて開催された(開催委員長:中部大学・竹森一正)。今回の関西・中部部会では,北海道・関東からの参加を含め,4名の自由論題と統一論題が行われ,約40名の研究者による活発な質疑応答が展開された。
■■自由論題報告第1部(院生セッション)
 ■■ 第1報告 第1報告では,井上和子氏(立教大学大学院)より「工業簿記と原価計算との有機的な結合による原価管理事例の考察」と題する研究報告がなされた。本報告では,標準原価計算を取り巻く現状を整理した上で,企業における事例,標準原価計算による原価差異分析,標準原価計算の活用による原価管理,標準原価を基軸とする労務管理の展開について考察が行われた。これらの考察を踏まえ,長期の企業経営という視点に立脚した場合,会計・原価計算は,本来,将来へ向けての実績計算にこそ意味を持つものであることが主張された。
■■ 第1報告 第1報告では,井上和子氏(立教大学大学院)より「工業簿記と原価計算との有機的な結合による原価管理事例の考察」と題する研究報告がなされた。本報告では,標準原価計算を取り巻く現状を整理した上で,企業における事例,標準原価計算による原価差異分析,標準原価計算の活用による原価管理,標準原価を基軸とする労務管理の展開について考察が行われた。これらの考察を踏まえ,長期の企業経営という視点に立脚した場合,会計・原価計算は,本来,将来へ向けての実績計算にこそ意味を持つものであることが主張された。
■■ 第2報告 第2報告では,梅田浩二氏(名古屋市立大学大学院)より,「海外子会社からの研究開発費回収方法に関する考察─移転価格税制と研究開発費負担の公平性の視点から─」と題する研究報告がなされた。本報告では,研究開発費の回収にあたり,現状では,ライセンス契約に基づくロイヤルティによる単一の方法で回収する企業が最も多いが,国際税務と開発費負担の公平性の観点からみれば,無形資産形成と費用分担契約,メディアへの転写作業と役務提供契約,無形資産の利用とライセンス契約,をそれぞれ対応させ,研究開発の各プロセスと最もよく適合する回収方法を複合的に選択することが望ましいと主張された。
■■自由論題報告第2部
 ■■第1報告 第1報告は,威知謙豪(中部大学)より,「特別目的事業体の連結会計基準の厳格化と実体的裁量行動」と題する研究報告がなされた。本報告では,一定の要件を満たす特別目的事業体を連結範囲から除外する例外規定の厳格化に伴い,その影響が相対的に高い企業においては,例外規定を利用した取引を取りやめる傾向にあることが確認された。一方で,早期適用や,今後の経営目標として採用される各種指標の算定の際に,一定の要件を満たす特別目的事業体を連結範囲に含めるか否かについては,例外規定の厳格化の影響の高低との一貫した関係は見られないことが報告された。
■■第1報告 第1報告は,威知謙豪(中部大学)より,「特別目的事業体の連結会計基準の厳格化と実体的裁量行動」と題する研究報告がなされた。本報告では,一定の要件を満たす特別目的事業体を連結範囲から除外する例外規定の厳格化に伴い,その影響が相対的に高い企業においては,例外規定を利用した取引を取りやめる傾向にあることが確認された。一方で,早期適用や,今後の経営目標として採用される各種指標の算定の際に,一定の要件を満たす特別目的事業体を連結範囲に含めるか否かについては,例外規定の厳格化の影響の高低との一貫した関係は見られないことが報告された。
■■第2報告 第2報告では,高瀬智章氏(広島国際大学)より,「公的病院の事業評価─政策医療費と収益医療費区分の必要性─」と題する研究報告がなされた。本報告では,公的病院の適切な業績評価に有用性を発揮する指標としての会計情報という視点から,公的病院の会計情報のあり方に関する指摘と提案がなされている。考察の結果,公的病院の主目的は「政策医療の実施」にあることから,副次的な活動である「収益医療」とを区分した区分表示型損益計算書の有用性が示唆された。
■■統一論題テーマ 「『絆』の時代における環境管理会計の今日と展望」
(座長:吉村文雄氏(金沢大学名誉教授),司会:竹森一正(中部大学))

2011年の大震災以来,私達は,放射能の不安に代表される暗い将来展望と不確実性が増す社会状況の中で生活を強いられています。しかし,それ故にでしょうか,人は絆を求め,愛を求め,友情を求める気運が満ちるようになっています。この中で「光につなぐ梯子」を懸命に,いろいろな分野で,探し,構築しようとの試みも見過ごすべきではないと考えます。幸いに私たちは管理会計という企業の根本を形成する基盤を専門としており,この知見は今後,強力な指導原理となることを見過ごしてはなりません。私達開催委員会は,この混迷の中で進展と深化の根源となる管理会計の研究エリアとして環境管理会計に着目し,また,時代状況を克服する意味での「絆」をキーワードとして,統一論題テーマを設定致しました。
■■第1報告 統一論題第1報告では,中嶌道靖氏(関西大学教授)より「MFCAのサプライチェーンへの展開」と題する研究報告がなされた。本報告では,MFCA(マテリアルフロー・コスト会計)をサプライチェーンに拡大しようとする日本企業の事例を中心に,MFCAのISO化による世界への普及,東アジアを中心としたMFCA のサプライチェーンへの展開の実現に向けた課題について検討がされ,そのうえで,MFCAによるグローバルな資源生産性の意義について考察が行われた。現在,日本企業以外にも,ISO14051をきっかけとして,東アジア企業においてもMFCAのサプライチェーンへの展開が行われており,これらを踏まえると,MFCAを1つのトリガーとして環境管理会計の研究および企業活動の中での繋がり・絆ができつつあることが述べられた。
■■第2報告 統一論題第2報告では,長岡正氏(札幌学院大学教授)より「物流環境管理会計の展開」と題する研究報告がなされた。本報告では,現在の環境管理会計は,一般に製造を対象としても物流までは対象としていないことから,輸送量削減を手段とする物流の取り組みは,生産量を所与とする製造の取り組みよりも効果が期待できると指摘された。その上で,物流コスト管理を目的とした物流管理会計,荷主の視点から実施するグリーン物流の取り組み,および製造を対象とする環境管理会計の3領域について,物流を対象とする環境管理会計の可能性の観点からの考察が行われ,同時削減を示す物流を対象としたエコ効率性の試案の1つとして,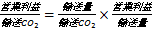 という評価指標が提案された。
という評価指標が提案された。
■■第3報告 統一論題第3報告では,今井範行氏(名城大学客員教授)より「環境管理会計とジャスト・イン・タイム経営」と題する研究報告がなされた。本報告では,トヨタ生産システム(TPS)をベースとした,ものづくり経営(=ジャスト・イン・タイム経営)という視点から,環境管理会計の今後の実務的課題について検討がおこなわれた。外部環境会計では,ものづくり現場の環境競争力の練磨には一定の限界があることから,最少資源で最大価値の創出を志向する環境システムとしてTPSを位置づけ, Jコスト,利益ポテンシャル,デュアルモード管理会計,TPSとマテリアルフロー・コスト会計の統合化,といったジャスト・イン・タイム経営に整合する環境管理会計の構築に,今後の環境管理会計の発展の可能性があることが述べられた。
■■ 報告者・司会者の先生方のご協力により,自由論題報告,統一論題報告および討論会をほぼ時間通りに進行することができた。そして,それぞれの報告に対しては活発な質疑応答がなされ,充実した部会研究報告となった。
威知 謙豪 (中部大学)

 ■■ 2012年度第1回企業研究会は,2012年7月20日(金)に株式会社北海道熱供給公社の札幌駅南口エネルギーセンターにおいて開催されました。平日における札幌での開催ということもあって10名の参加者となりましたが,非常に活発な意見交換がなされました。なお,同公社は株式会社北海道ガスの連結子会社にあたり,今回の企業研究会の開催の準備に際しては,北海道ガス・監査室長の山崎秀樹様からご支援を頂きました。
■■ 2012年度第1回企業研究会は,2012年7月20日(金)に株式会社北海道熱供給公社の札幌駅南口エネルギーセンターにおいて開催されました。平日における札幌での開催ということもあって10名の参加者となりましたが,非常に活発な意見交換がなされました。なお,同公社は株式会社北海道ガスの連結子会社にあたり,今回の企業研究会の開催の準備に際しては,北海道ガス・監査室長の山崎秀樹様からご支援を頂きました。 ■■ その後,センター長の案内のもと,全体で4800m2にもわたるプラント設備の一部について見学が行われました。参加者は,札幌駅の地下にありながら,普段では決して見ることのできないタービン発電機やボイラー施設,張り巡らされた配管などの巨大な設備を前に,質問を交えながら熱心に見学をしていました。
■■ その後,センター長の案内のもと,全体で4800m2にもわたるプラント設備の一部について見学が行われました。参加者は,札幌駅の地下にありながら,普段では決して見ることのできないタービン発電機やボイラー施設,張り巡らされた配管などの巨大な設備を前に,質問を交えながら熱心に見学をしていました。

 ■■第1報告では,島田美智子氏(下関市立大学教授)より,「財務報告の管理会計化―Zambon[2011]の所説に寄せて―」と題する報告があり,Zambon,S.[2011] The managerialisation of Financial Reporting : an introduction to a destabilising accounting change, Financial Reporting, Supplement.を手掛かりに,現代の財務報告においては,IT技術の発展や自発的ディスクロージャーの進展を背景に,経営者の視点にもとづく管理会計情報の利用が重要性を増し,企業特殊的情報の開示,業績指標の多様化,財務会計領域の拡張,理論と実務の緊密化などが進んでおり,財務会計と管理会計の相互作用的進化を前提とした制度設計や会計教育の必要性が主張された。
■■第1報告では,島田美智子氏(下関市立大学教授)より,「財務報告の管理会計化―Zambon[2011]の所説に寄せて―」と題する報告があり,Zambon,S.[2011] The managerialisation of Financial Reporting : an introduction to a destabilising accounting change, Financial Reporting, Supplement.を手掛かりに,現代の財務報告においては,IT技術の発展や自発的ディスクロージャーの進展を背景に,経営者の視点にもとづく管理会計情報の利用が重要性を増し,企業特殊的情報の開示,業績指標の多様化,財務会計領域の拡張,理論と実務の緊密化などが進んでおり,財務会計と管理会計の相互作用的進化を前提とした制度設計や会計教育の必要性が主張された。 ■■第2報告では,大下丈平氏(九州大学教授)より,「コントロールのパラドックスと管理会計―『レレバンス・ロスト』の意義を考える―」と題する報告があり,『レレバンス・ロスト』刊行から四半世紀を迎えた現在,依然として管理会計は,会計領域内部からの批判,生産現場からの批判,および資本市場からの批判,という3つの「レレバンス・ロスト」に直面しているとの問題提起がなされ,この3つの矛盾した批判に応えていく方向性として,TDABC,VBM,COSO-ERMなどの意義,ならびにコントロールがガバナンスやCSRを取り込みつつ,それらを規律付けていく必要があるとの主張がなされた。
■■第2報告では,大下丈平氏(九州大学教授)より,「コントロールのパラドックスと管理会計―『レレバンス・ロスト』の意義を考える―」と題する報告があり,『レレバンス・ロスト』刊行から四半世紀を迎えた現在,依然として管理会計は,会計領域内部からの批判,生産現場からの批判,および資本市場からの批判,という3つの「レレバンス・ロスト」に直面しているとの問題提起がなされ,この3つの矛盾した批判に応えていく方向性として,TDABC,VBM,COSO-ERMなどの意義,ならびにコントロールがガバナンスやCSRを取り込みつつ,それらを規律付けていく必要があるとの主張がなされた。 ■■第3報告では,新茂則氏(中村学園大学教授)より,「不動産企業の時価情報開示と株価―賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用による株価の影響―」と題する報告があり,近年の会計制度改革による時価情報開示が株価に反映されているのかという問題意識のもと,賃貸等不動産会社をサンプルとして,不動産会社の保有賃貸等不動産の含み益の実態,日経平均株価やTOPIXと特定銘柄株価の相関,決算発表前後の出来高や株価の変動パターン,賃貸空室率と株価の関係,PER・PBR・ROA・ROEの推移などを検証し,株式市場は効率的であるとの見解を示された。
■■第3報告では,新茂則氏(中村学園大学教授)より,「不動産企業の時価情報開示と株価―賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用による株価の影響―」と題する報告があり,近年の会計制度改革による時価情報開示が株価に反映されているのかという問題意識のもと,賃貸等不動産会社をサンプルとして,不動産会社の保有賃貸等不動産の含み益の実態,日経平均株価やTOPIXと特定銘柄株価の相関,決算発表前後の出来高や株価の変動パターン,賃貸空室率と株価の関係,PER・PBR・ROA・ROEの推移などを検証し,株式市場は効率的であるとの見解を示された。