■■ 日本管理会計学会2015年度全国大会は、平成27年8月28日(金)から30(日)の3日間、近畿大学東大阪キャンパスにおいて開催された。28日には、学会賞審査委員会、常務理事会、理事会、理事懇親会が開催された。29日は、午前9時30分から4会場に分かれ、計16の自由論題報告が行われた。午後には、会員総会、特別講演に続き、統一論題報告と討論が行われた。統一論題報告終了後、午後6時すぎより、東大阪キャンパス内のブロッサムカフェにて会員懇親会が開催され、会員の懇親を深めた。翌30日は、午前9時30分から5会場に分かれ、計16の自由論題報告が行われ、これと並行して、スタディ・グループと産学共同研究グループによる報告が行われた。
■■ 学会賞
功績賞:上總康行氏(京都大学名誉教授)、小林啓孝氏(早稲田大学)
文献賞:伊藤和憲氏(専修大学)
『BSCによる戦略の策定と実行:
事例で見るインタンジブルズのマネジメントと統合報告への管理会計の貢献』同文館出版.
論文賞:木村史彦氏(東北大学)
「事業内容と利益マネジメント-利益マネジメントの業種間比較を通じて-」
『管理会計学』第23巻第1号.
奨励賞:堀井悟志氏(立命館大学)
「予算管理とイノベーションの創出」『管理会計学』第23巻第1号.
■■ 統一論題・討論「コスト・ビヘイビアと原価計算」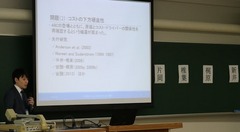
片岡洋人氏(明治大学)を座長とする統一論題報告が行われた。テーマは,「コスト・ビヘイビアと原価計算」であった。片岡洋人座長による開題の後、次の3つの報告が行われた。
■ 統一論題報告(1) :椎葉 淳氏(大阪大学大学院)
「コスト構造と企業リスク:近年の理論・実証研究からの示唆」
本報告では,企業リスクとの関係からコスト構造に関する近年の研究を概観するとともに,今後の研究の方向性について議論された。椎葉氏は,(1)経営者のインセンティブを考慮したコスト構造のモデルへの拡張,(2)生産関数としての企業理論とエージェンシー理論の融合,という二つの必要性を指摘された。
■ 統一論題報告(2) :梶原武久氏(神戸大学大学院)
「コストマネジメント行動とコスト・ビヘイビアの裏側に迫る」
本報告では,近年におけるコスト・ビヘイビア研究の展開を概観した上で,今後の研究の方向性として,(1)財務会計研究と管理会計研究の接合,(2)コスト・ビヘイビア研究とコストマネジメント研究の接合,という二つの方向性が提示された。梶原氏はそのうち(2)に注目し,その試みの一つとして,日本ロジスティックスシステム協会による物流コスト調査のデータを用いた分析結果を示した。
■ 統一論題報告(3) :新井康平氏(群馬大学)
「管理会計研究における階層線形モデル(HLM)の有用性の探求:文献レビューによる検討」
本報告では,管理会計研究・実務における階層線形モデル(HLM)の有用性を探求することを目的として,HLMを企業単位ではなく,よりミクロな単位の財務数値に適用する上での可能性と注意点が議論された。これらを踏まえて、HLMの管理会計・原価計算研究および実務への含意が議論された。
■ 統一論題討論
統一論題報告の後,続けて統一論題討論が行われた。各報告者による要約の報告および補足事項に続き,片岡洋人座長から問題提起がなされた。その後,参加者との活発な質疑応答が行われた。
■■ 次回の日本管理会計学会年次全国大会は、明治大学において2016年8月31日(水)から9月2日(金)にかけて開催される予定である。
2015年度全国大会実行委員会 委員長 安酸建二(近畿大学)
