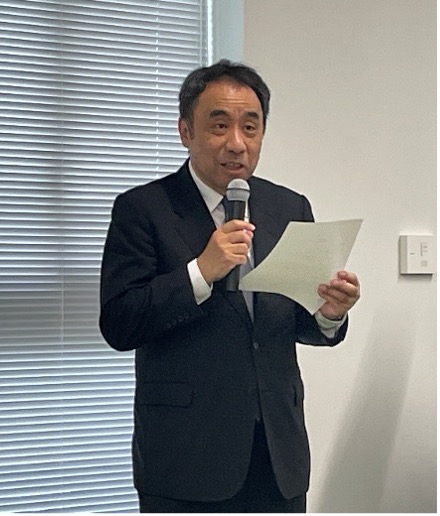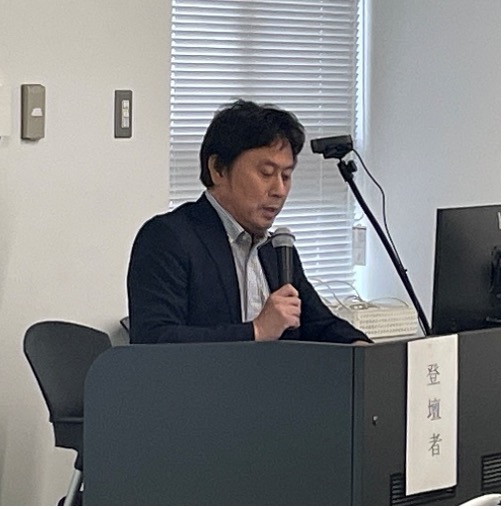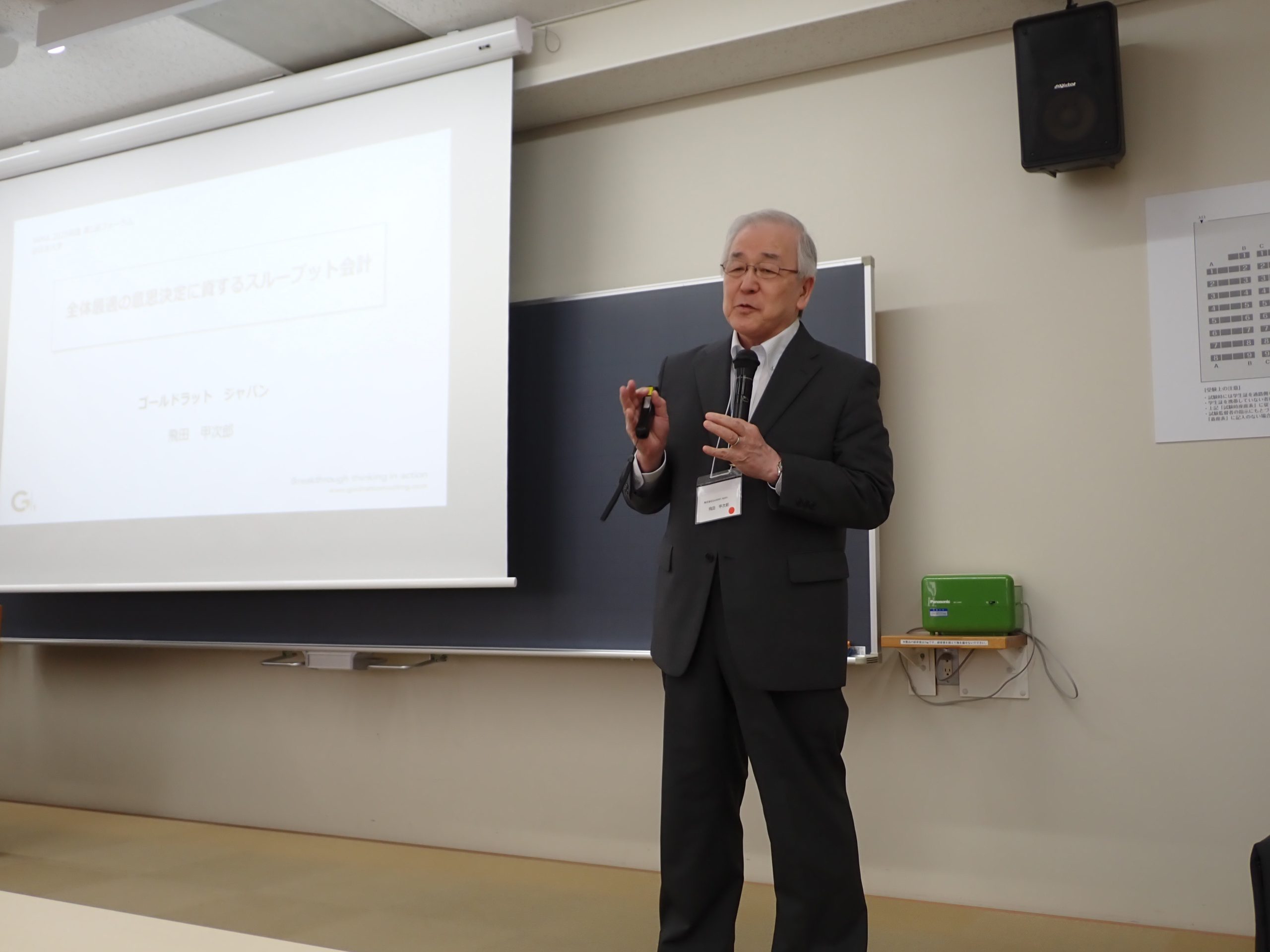2025年度第1回フォーラムは,2025年4月26日(土)14時00分から16時30分まで,日本大学商学部において対面形式で開催された。開会に先立ち,本学会会長 﨑章浩氏(東京国際大学)よりご挨拶を賜り,引き続き,関谷浩行(日本大学)の司会によりプログラムが進行した。

﨑章浩会長挨拶
本フォーラムでは,特別講演として飛田甲次郎氏(株式会社Goldratt Japan・パートナー)をお迎えし,あわせて根本萌希氏(鹿児島国際大学)・梅田充氏(金沢星稜大学)による共同研究報告,および友寄隆哉氏(産業能率大学)による研究報告の計3件が行われた。
当日は,非会員,学部生・大学院生17名を含む70名の参加があり,いずれの特別講演・研究報告に対しても活発な質疑応答が交わされ,大変有意義な議論が展開された。フォーラム終了後には懇親会も催され,参加者間の親睦が一層深まった。盛況のうちに本フォーラムは無事に閉会した。
〔特別講演〕
◎講演者:飛田甲次郎氏(株式会社Goldratt Japan・パートナー)
◎講演題目:全体最適の意思決定に資するスループット会計
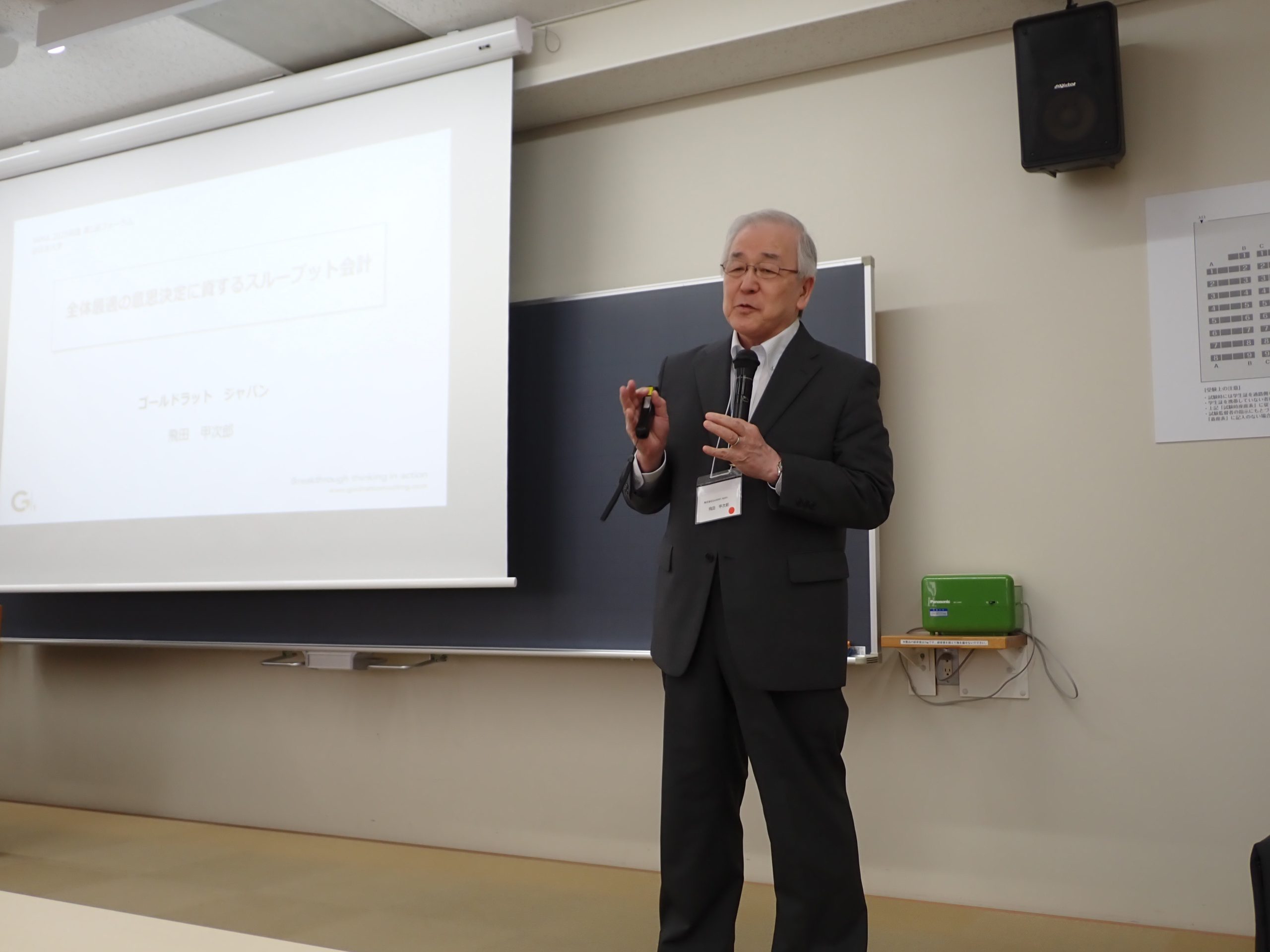
飛田甲次郎氏による特別講演
飛田氏は,制約理論(TOC)に基づくスループット会計をテーマに講演を行い,企業活動における全体最適の意思決定の重要性を説いた。まず,組織の目的を「現在から将来にわたってお金を稼ぎ続けること」,さらに「すべてのステークホルダーにとっての価値を上げること」と定義され,その実現には,オペレーションの主要な目的をフロー(リードタイム)の改善におくべきであると主張した。
制約理論の基本的な考え方として,部分最適を排除し,全体の流れを阻害する制約(ボトルネック)に集中すべきことが必要である。作業の過剰投入やマルチタスクの弊害が生産性や品質に与える悪影響について,具体例を交えて説明された。
続いて,スループット会計の特徴について解説された。スループットとは「販売によって,システム(企業)がお金を作り出すレート」であり,「販売するまでカウントしない」,「配賦を一切しない」,「スループットは制約によって律速される」といった特徴を有する点が強調された。このような仕組みによって,従来の会計手法では捉えにくかった収益性や意思決定基準を,より明快かつ直感的に把握できることが示された。とりわけ,「制約消費時間当たりのスループット」を指標とすることで,製品別の収益性比較,内製か外注かの判断,投資の優先順位づけが合理的に行えることが示された。
具体的な実践例として,株式会社ユニフローの事例が紹介された。同社の主な販売製品はスイングドアで,マーケットシェアは約8割である。同社では,設計部門がボトルネックとなり,受注後の設計変更や手戻りが多発し,リードタイムの長期化と市場機会の逸失が課題であった。そこで同社は,限界利益率だけでなく制約資源の使用量を加味して意思決定を行い,フローの最適化を図った。その結果,売上高は40%増加し,営業利益率は0.5%から8.4%へと16倍にまで向上した。
講演の締めくくりとして飛田氏は,今後の経営には専門的な会計知識がなくとも直感的に理解でき,現場でも活用可能なシンプルかつ全体最適志向の意思決定会計が必要不可欠であると述べられ,スループット会計と制約理論の積極的な導入を呼びかけた。
◎参考ホームページ:『ザ・ゴール』アニメオンデマンドURL:
https://www.goldrattchannel.net/premiere
〔研究報告〕
第1報告
◎報告者:根本萌希氏(鹿児島国際大学)・梅田充氏(金沢星稜大学)
◎報告題目:BSCの導入が離職率と従業員エンゲージメントに与える影響:混合研究法に基づくシングルケーススタディ

根本萌希氏による研究報告
本報告では,医療機関における人材確保の難しさや,従業員エンゲージメントに対応する手法として,バランスト・スコアカード導入の効果を検証したシングルケーススタディの成果が紹介された。リサーチサイトは,東京都清瀬市にある社会福祉法人慈生会ベトレヘムの園病院(許可病床数96床)であり,混合研究法に基づき,定量・定性の両面から長期的に分析が行われた。
研究は3段階で構成され,第1にバランスト・スコアカード導入と体制整備,第2に運用と研修プログラムの実施,第3に人的資源の成果との関係性の検討が行われた。特にバランスト・スコアカードのコミュニケーション機能に注目し,戦略のカスケードや部門間の情報共有,外部ステークホルダーとの関係構築といった組織的効果が取り上げられた。分析手法には中断時系列分析,ウィルコクソン符号順位検定,スピアマン順位相関分析を用いられ,導入前後の統計的変化が検証された。
結果として,病院全体および看護師の離職率は有意に低下し,エンゲージメントスコアは明確に向上したことが示された。両者の間には強い負の相関が確認され,バランスト・スコアカードが人材マネジメントに資する有効な手段であることが示唆された。一方で,単一事例に基づく一般化の限界や,指標変更といった方法論的制約も指摘されている。今後は複数の医療機関を対象とした比較研究や,医療の質や患者安全性との関連性の検討,さらには職員の意識変容プロセスに焦点を当てた研究の展開が期待される。
第2報告
◎報告者:友寄隆哉氏(産業能率大学)
◎報告題目:企業価値創造プロセスの可視化

友寄隆哉氏による研究報告
産業能率大学は,90年以上にわたって企業の研修に講師を派遣し,実務家教育に豊かな実績を築いてきた。友寄氏は,同大学における企業研修での経験を出発点として,管理会計を中核に据えた企業価値創造プロセスの可視化に取り組み,新たな教材および講座の開発を進めている。
本報告ではとくにバランスト・スコアカードと統合報告を連携させることにより,企業価値創造の構造を体系的に捉え,戦略の策定と実行を一体的に支援するマネジメントの枠組みについての文献研究の成果が報告された。具体的には,エーザイ株式会社の統合報告書(2021年度より「価値創造レポート」に改称)を分析対象とし,戦略マップの活用により,財務情報と非財務情報の因果関係が可視化され,社内における情報の結合性が向上している点が指摘された。
現在,日本企業におけるバランスト・スコアカードの導入率は依然として低水準にあるものの,エーザイで実践されたように統合報告との組み合わせにより,統合思考の醸成,情報の結合性の向上,ステークホルダーとの関係強化,そしてマテリアリティの可視化など,多面的な効果が期待できることが示された。
結論として,統合報告は単なる情報開示の手段にとどまらず,ステークホルダーによる戦略的情報活用を支えるマネジメント・ツールとして再定義されるべきであると提言された。戦略マップを活用した情報の開示と情報利用の意義が強調され,経営戦略の実行と社会課題の解決とを両立させる重要性が指摘された。
文責:関谷浩行(日本大学)
![]() fukuoka-u.ac.jp)までご連絡ください。
fukuoka-u.ac.jp)までご連絡ください。