■■ 日本管理会計学会2013年度第1回フォーラムが,2013年4月13日(土)に南山大学において開催された。園田智昭氏(フォーラム担当副会長,慶應義塾大学)の開会の挨拶に続いて,第1部の研究報告が開始された。研究報告の部では,星野優太氏(名古屋市立大学)の司会のもと,孫美レイ(流通科学大学),木村史彦氏(東北大学),川野克典氏(日本大学)による報告が行われ,活発な議論が展開された。第2部の企業講演は,吉澤和秀氏(中京テレビ放送 常勤監査役)によって「テレビ局の経営と管理」というタイトルで講演が行われた。その後,会場を移して懇親会が行われた。
■■ 第1報告:孫美レイ氏(流通科学大学)
「内部統制制度の導入効果に関する一考察 -4社の事例-」
 孫氏の報告は,アメリカの不正会計に端を発する内部統制という経済制度がアジアの経済的文脈のなかでどのような効果を果たしているのかについての日本企業を対象とした分析の報告であった。
孫氏の報告は,アメリカの不正会計に端を発する内部統制という経済制度がアジアの経済的文脈のなかでどのような効果を果たしているのかについての日本企業を対象とした分析の報告であった。
孫氏は,企業へのインタビューによる質的研究方法を用いて内部統制制度の効果を明らかにしている。4社をインタビューし,当該企業において内部統制制度の効果が現れるとすればどこで効果が現れているのか,また効果が現れないのであれが問題の所在はどこにあるのかなどについて企業別に検討した。
孫氏は,インタビュー調査の結果について,次のようにまとめられた。A社は内部統制制度による不正防止の効果に対して懐疑的であるが,業務の有効性や効率性の向上効果に対しては肯定的な見解を持っている。B社は内部統制制度の導入に課題に感じており,制度対応に加えて自社独自の方法も取り入れながら不正の防止や業務効率の向上を図っている。C社は内部統制制度の導入前から業務のオペレーションが成熟化し,業務の効率性も高く,内部統制制度による業務効率性のさらなる向上は達成できていない。また不正防止の効果に対して懐疑的である。D社は内部統制制度による業務の効率性の向上に肯定的である。
■■ 第2報告:木村史彦氏(東北大学)
「利益マネジメントの業績間比較」
 木村氏の報告は,日本の上場会社における業種ごとの利益マネジメントの傾向と,業種間の差異に影響する要因を明らかにしようとするものであった。研究方法は以下のとおりである。まず,各業種の利益マネジメントの傾向を国際比較研究の手法の方法を援用して定量化し業種間で比較する。その上で,業種ごとの利益マネジメントの水準に影響を及ぼす要因として,(1) 政治コスト,(2) 資金調達方法,(3) 投資機会集合,(4) 会計上のフレキシキビリティ,(5) 業種内の競争性,を取り上げ,業種ごとの利益マネジメントの水準との関係を分析する。分析対象は,2004年から2011年までの日本企業25,208社であった。
木村氏の報告は,日本の上場会社における業種ごとの利益マネジメントの傾向と,業種間の差異に影響する要因を明らかにしようとするものであった。研究方法は以下のとおりである。まず,各業種の利益マネジメントの傾向を国際比較研究の手法の方法を援用して定量化し業種間で比較する。その上で,業種ごとの利益マネジメントの水準に影響を及ぼす要因として,(1) 政治コスト,(2) 資金調達方法,(3) 投資機会集合,(4) 会計上のフレキシキビリティ,(5) 業種内の競争性,を取り上げ,業種ごとの利益マネジメントの水準との関係を分析する。分析対象は,2004年から2011年までの日本企業25,208社であった。
木村氏は,分析結果について次のようにまとめられた。業種間で利益マネジメントの水準に顕著な差異が見られる。さらに,政治コストが大きい,負債による資金調達のウエイトが高い業種では,利益マネジメントが実施される可能性が高い。また,この結果は,異なる業種分類を用いた場合でも頑健であった。
■■ 第3報告:川野克典氏(日本大学)
「進化を止めた日本企業の管理会計」
 川野氏の報告は,2011から2012年に東京証券取引所上場会社に対して実施したアンケート調査(回答数は190社,回収率9.3%)にもとづいて行われた。
川野氏の報告は,2011から2012年に東京証券取引所上場会社に対して実施したアンケート調査(回答数は190社,回収率9.3%)にもとづいて行われた。
川野氏は,この調査結果を次のようにまとめられた。日本企業は,全体として極めて保守的であり,新しく提案された管理会計手法の採用には消極的である。一方で,外部からの圧力,すなわち,法律の改正や会計基準の公表等があると,日本企業はこれに対応すべく管理会計制度の見直しを行う。国際会計基準の日本への導入については,適用時期,範囲等,見通しがつかない状況が続いている。その結果,日本基準ベースの管理会計を構築すべきか,国際会計基準に対応した管理会計を構築すべきかの判断ができなくなってしまい,管理会計の見直しを進めようとする意志のある企業でも,見直しに着手すらできず,これらの結果,日本企業の管理会計の進化が止まってしまっている。
また,今後の日本企業の管理会計に求められるものとして,統合報告(Integrated Reporting)に学び,経営成績と財政状態の向上の最終結果(アウトカム)としての企業価値向上に結び付く,ストーリー化された統合的な管理会計体系の構築を指摘した。
■■ 企業講演:吉澤和秀氏(中京テレビ放送 常勤監査役)
「テレビ局の経営と管理」
 吉澤氏の講演は,「経営と管理」の観点から,テレビ局の経営状況の推移とCSRの2点に絞って行われた。テレビ局の経営状況については,以下のように述べられた。テレビ業界は創業以来,日本経済の発展に伴って成長し放送事業の多様化を進めてきた。日本国内のメディアを広告費で見ると,2012年1年間の広告費は,およそ5兆9000億円で,その内マスコミ4媒体と言われるテレビ・新聞・雑誌・ラジオが47%,テレビは30%を占めている。テレビ業界は,創業以来日本経済の発展に伴って成長してきたが,WEBなどメディアの多様化の影響から売上は2006年度をピークに減少傾向に入り,リーマンショックの翌年は,ピーク時の87%まで落ち込んだ。長いトレンドで見れば漸減傾向を覚悟しなければならず,各局は,映画やDVD,アイスショーなど,放送を活用した事業収入の創出を工夫している。
吉澤氏の講演は,「経営と管理」の観点から,テレビ局の経営状況の推移とCSRの2点に絞って行われた。テレビ局の経営状況については,以下のように述べられた。テレビ業界は創業以来,日本経済の発展に伴って成長し放送事業の多様化を進めてきた。日本国内のメディアを広告費で見ると,2012年1年間の広告費は,およそ5兆9000億円で,その内マスコミ4媒体と言われるテレビ・新聞・雑誌・ラジオが47%,テレビは30%を占めている。テレビ業界は,創業以来日本経済の発展に伴って成長してきたが,WEBなどメディアの多様化の影響から売上は2006年度をピークに減少傾向に入り,リーマンショックの翌年は,ピーク時の87%まで落ち込んだ。長いトレンドで見れば漸減傾向を覚悟しなければならず,各局は,映画やDVD,アイスショーなど,放送を活用した事業収入の創出を工夫している。
CSRについては,テレビ局の経営にとって最も重要なのは放送倫理であるとして,次のように説明された。放送は,人の命や健康あるいは人権に係わる情報を取り扱い視聴者に届けているので,その情報が万一,誤っていたり,放送したことが何らかの被害を招く結果とならないよう放送に当たっては,番組制作の現場で2重3重のチェックをしている。また,放送倫理を専門とする部署でスクリーニングし,且つ放送法で定められた外部有識者による番組審議会で定期的に評価されている。放送倫理に関する規定集やマニュアルは各種整備・更新しているが,何と言っても日々の放送活動の中でスタッフが高い意識を持って業務に当たることが肝心で,スタッフへの放送倫理研修は頻繁に実施している。放送倫理の遵守はテレビ局のCSRの基本と言える。
最後に,BCPにふれ,次のように結ばれた。放送局は南海トラフを震源域とする巨大地震をはじめとした非常時に視聴者に情報を伝える放送機能の継続が最重要であることからBCP-B(Business Continuity Plan of Broadcasting)の概念を基本として,放送のための要員・設備の他,電力供給が停止した場合の非常用発電などの体制を整えるとともに,非常時を想定した訓練を行うなど社会的使命を果たすべく取り組んでいる。
斎藤孝一(実行委員長 南山大学)

 ■■ 日本管理会計学会2012年度第3回フォーラムは,玉川大学を会場として,2012年12月8日(土)に開催された(実行委員長:山田義照氏)。今回のフォーラムのテーマは「ものづくりの管理会計の再考」とされ,日本のものづくりと管理会計の関係に焦点を当てた研究報告と企業講演が行われた。参加者は70名を超え,熱のこもった議論が繰り広げられた。第1部の研究報告では,園田智昭氏(慶応義塾大学)の司会のもと,原慎之介(一橋大学大学院),田坂公氏(久留米大学),中嶌道靖氏・木村麻子氏(関西大学)の3組が報告された。第2部の企業講演では,司会を伊藤和憲氏(専修大学)にバトンタッチし,織田芳一氏(富士ゼロックス株式会社 調達本部原価管理部)が講演された。その後,場所を移して懇親会が行われ,1年間の学会活動を振り返りながら,今回のフォーラムを惜しみつつ散会となった。
■■ 日本管理会計学会2012年度第3回フォーラムは,玉川大学を会場として,2012年12月8日(土)に開催された(実行委員長:山田義照氏)。今回のフォーラムのテーマは「ものづくりの管理会計の再考」とされ,日本のものづくりと管理会計の関係に焦点を当てた研究報告と企業講演が行われた。参加者は70名を超え,熱のこもった議論が繰り広げられた。第1部の研究報告では,園田智昭氏(慶応義塾大学)の司会のもと,原慎之介(一橋大学大学院),田坂公氏(久留米大学),中嶌道靖氏・木村麻子氏(関西大学)の3組が報告された。第2部の企業講演では,司会を伊藤和憲氏(専修大学)にバトンタッチし,織田芳一氏(富士ゼロックス株式会社 調達本部原価管理部)が講演された。その後,場所を移して懇親会が行われ,1年間の学会活動を振り返りながら,今回のフォーラムを惜しみつつ散会となった。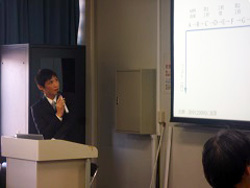 原氏は,既存の会計理論は原価低減に偏重していて,在庫低減やリードタイム短縮活動の評価に必ずしも結びついていないと主張され,Jコストを現場に導入することの意義について述べられた。Jコスト論は,トヨタ生産方式を会計的に評価することを目的として,田中正知氏(ものつくり大学名誉教授)によって提唱されたものである。現場のリードタイムを短縮する効果を財務的数値とリンクさせることを目的として作られた理論であるという。
原氏は,既存の会計理論は原価低減に偏重していて,在庫低減やリードタイム短縮活動の評価に必ずしも結びついていないと主張され,Jコストを現場に導入することの意義について述べられた。Jコスト論は,トヨタ生産方式を会計的に評価することを目的として,田中正知氏(ものつくり大学名誉教授)によって提唱されたものである。現場のリードタイムを短縮する効果を財務的数値とリンクさせることを目的として作られた理論であるという。 田坂氏は,円高の問題を始めとする厳しい企業環境の変化のなかで,日本の企業が国内から海外へ出て行ってしまっているという現状を憂え,原価企画がどのようにグローバル企業に対応してきているのかについて報告された。報告では,原価企画の先駆的企業である自動車部品メーカーA社に対する調査を一つの事例として,特に新興国向けにどのような原価企画が展開されているのかについて述べられた。
田坂氏は,円高の問題を始めとする厳しい企業環境の変化のなかで,日本の企業が国内から海外へ出て行ってしまっているという現状を憂え,原価企画がどのようにグローバル企業に対応してきているのかについて報告された。報告では,原価企画の先駆的企業である自動車部品メーカーA社に対する調査を一つの事例として,特に新興国向けにどのような原価企画が展開されているのかについて述べられた。 中嶌氏と木村氏の共同研究において中嶌氏が中心となり報告された。氏は,MFCAが物量管理とコスト情報を組み合わせて行われる管理会計技法の一つとして位置づけられることを説明され,(1)日本のものづくりの評価(マテリアルロスの発見),(2)日本企業のものづくりを強化する(マテリアルロスの削減),(3)MFCAの有用性とは(改善点の拡大と拡張・コスト削減と結びつく技術革新)という3つの視点で報告された。
中嶌氏と木村氏の共同研究において中嶌氏が中心となり報告された。氏は,MFCAが物量管理とコスト情報を組み合わせて行われる管理会計技法の一つとして位置づけられることを説明され,(1)日本のものづくりの評価(マテリアルロスの発見),(2)日本企業のものづくりを強化する(マテリアルロスの削減),(3)MFCAの有用性とは(改善点の拡大と拡張・コスト削減と結びつく技術革新)という3つの視点で報告された。 ■■ 日本管理会計学会2012年度第2回フォーラムは,北海道大学を会場として,2012年7月21日(土)に開催された(実行委員長:篠田朝也氏)。今回のフォーラムでは,統一論題が設定されていなかったものの,管理会計と会計実務の関係を強く意識した研究報告と企業講演が行われ,活発な議論が展開された。第1部の研究報告では,丸田起大氏(九州大学),藤本康男氏(フジモトコンサルティングオフィス合同会社代表社員,税理士),長坂悦敬氏(甲南大学)の3名が報告された。第2部の企業講演では,北海道で活躍している元気な企業で,社会貢献活動を積極的に展開されている企業のなかから,実行委員長の篠田氏が株式会社富士メガネに講演を依頼した経緯が説明されたのち,大久保浩幸氏(株式会社富士メガネ取締役,人事・総務部長)が講演された。その後,場所を移して懇親会が行われ,夏の北海道でのフォーラムを惜しみつつ散会となった。
■■ 日本管理会計学会2012年度第2回フォーラムは,北海道大学を会場として,2012年7月21日(土)に開催された(実行委員長:篠田朝也氏)。今回のフォーラムでは,統一論題が設定されていなかったものの,管理会計と会計実務の関係を強く意識した研究報告と企業講演が行われ,活発な議論が展開された。第1部の研究報告では,丸田起大氏(九州大学),藤本康男氏(フジモトコンサルティングオフィス合同会社代表社員,税理士),長坂悦敬氏(甲南大学)の3名が報告された。第2部の企業講演では,北海道で活躍している元気な企業で,社会貢献活動を積極的に展開されている企業のなかから,実行委員長の篠田氏が株式会社富士メガネに講演を依頼した経緯が説明されたのち,大久保浩幸氏(株式会社富士メガネ取締役,人事・総務部長)が講演された。その後,場所を移して懇親会が行われ,夏の北海道でのフォーラムを惜しみつつ散会となった。 丸田氏は,わが国における管理会計研究の発展に向けて,実務家と研究者との間で共同研究・共同開発が活発化されることの期待を表明するとともに,アクションリサーチに代表される関与型研究(interventionist research)にもとづいて実践されている共同研究「ソフトウェア開発における品質コストマネジメントの適用」の事例を紹介された。
丸田氏は,わが国における管理会計研究の発展に向けて,実務家と研究者との間で共同研究・共同開発が活発化されることの期待を表明するとともに,アクションリサーチに代表される関与型研究(interventionist research)にもとづいて実践されている共同研究「ソフトウェア開発における品質コストマネジメントの適用」の事例を紹介された。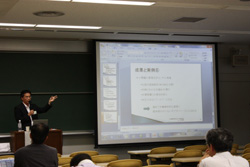 藤本氏は,地域に根差した企業を支援することによって地域経済の活性化に貢献するというミッションを実現するためには,中小製造業に管理会計を導入させることが重要であると主張された。氏が経営するコンサルタント会社では,経営者の意思決定に役立つ情報網の構築=「見える化」と,それを利用した経営改善のしくみを社内に定着させることを目的としており,経営者のみならず社員一人ひとりが「戦略」と「データ」にもとづいて考え行動する集団になることを目指しているという。氏は,この文脈から,オホーツク紋別にある水産加工(かまぼこ)会社に対する管理会計導入の事例を紹介された。
藤本氏は,地域に根差した企業を支援することによって地域経済の活性化に貢献するというミッションを実現するためには,中小製造業に管理会計を導入させることが重要であると主張された。氏が経営するコンサルタント会社では,経営者の意思決定に役立つ情報網の構築=「見える化」と,それを利用した経営改善のしくみを社内に定着させることを目的としており,経営者のみならず社員一人ひとりが「戦略」と「データ」にもとづいて考え行動する集団になることを目指しているという。氏は,この文脈から,オホーツク紋別にある水産加工(かまぼこ)会社に対する管理会計導入の事例を紹介された。 長坂氏は,製造関係との産学連携という視点から大学研究者として産業界にどのようなアクションが起こせるかという問題意識のもとで,管理会計のフレームワークやコントロール概念を深化・発展させる手掛かりとして,「融合コストマネジメント」(Fused Cost Management)というアプローチを提唱された。また,実務にインプリメントできる具体的なアクション研究をソリューションと捉えて,産学官の共同プロジェクトから開発・提案されたソリューションの事例を紹介された。
長坂氏は,製造関係との産学連携という視点から大学研究者として産業界にどのようなアクションが起こせるかという問題意識のもとで,管理会計のフレームワークやコントロール概念を深化・発展させる手掛かりとして,「融合コストマネジメント」(Fused Cost Management)というアプローチを提唱された。また,実務にインプリメントできる具体的なアクション研究をソリューションと捉えて,産学官の共同プロジェクトから開発・提案されたソリューションの事例を紹介された。 大久保氏は,メガネは医療用具であるという立場からお客様にメガネを提供していること,そのための人材養成をしていることを強調された。また,お客様の「見る喜び」という企業理念の具現化やノウハウの蓄積を一定のサービスレベルで保持して,売上を向上させていくためのソフトの開発が不可欠であると主張された。このソフトが富士メガネ総合情報システム(Fuji Total Information System,以下「FTIS」という。)であり,その導入経緯と機能の概要について説明された。
大久保氏は,メガネは医療用具であるという立場からお客様にメガネを提供していること,そのための人材養成をしていることを強調された。また,お客様の「見る喜び」という企業理念の具現化やノウハウの蓄積を一定のサービスレベルで保持して,売上を向上させていくためのソフトの開発が不可欠であると主張された。このソフトが富士メガネ総合情報システム(Fuji Total Information System,以下「FTIS」という。)であり,その導入経緯と機能の概要について説明された。 ■■ 日本管理会計学会2012年度第1回フォーラムが,2012年4月14日(土)に大阪成蹊大学・短期大学にて開催された(実行委員長:大阪成蹊短期大学 三浦徹志教授)。今回のフォーラムでは,斉藤孝一氏(南山大学)の司会もと,景山愛子氏(安田女子大学),平井裕久氏(高崎経済大学)・後藤晃範氏(大阪学院大学)の2報告が行われ,松尾貴巳氏(神戸大学)の司会のもと,国枝よしみ氏(大阪成蹊短期大学)・鹿内健一氏(大阪成蹊短期大学)・田中祥司氏(大阪成蹊短期大学非常勤講師・早稲田大学大学院),島吉伸氏(近畿大学)・安酸健二氏(近畿大学)・栗栖千幸氏(医療法人鉄蕉会亀田メディカルセンター経営管理本部 企画部経営企画室)の2報告(計4報告)が行われた。
■■ 日本管理会計学会2012年度第1回フォーラムが,2012年4月14日(土)に大阪成蹊大学・短期大学にて開催された(実行委員長:大阪成蹊短期大学 三浦徹志教授)。今回のフォーラムでは,斉藤孝一氏(南山大学)の司会もと,景山愛子氏(安田女子大学),平井裕久氏(高崎経済大学)・後藤晃範氏(大阪学院大学)の2報告が行われ,松尾貴巳氏(神戸大学)の司会のもと,国枝よしみ氏(大阪成蹊短期大学)・鹿内健一氏(大阪成蹊短期大学)・田中祥司氏(大阪成蹊短期大学非常勤講師・早稲田大学大学院),島吉伸氏(近畿大学)・安酸健二氏(近畿大学)・栗栖千幸氏(医療法人鉄蕉会亀田メディカルセンター経営管理本部 企画部経営企画室)の2報告(計4報告)が行われた。 フォーラムでは,園田智昭副会長(慶応義塾大学)から開催挨拶があり,続いて大阪成蹊短期大学 武蔵野實学長より歓迎の挨拶を頂いた。武蔵野学長は挨拶の中で,大阪成蹊大学・短期大学の歴史や建学の精神について触れられ,今回のフォーラムにおける発表内容との関連で,自然環境における長期的最適条件を守りながら,経済的な短期的最適条件を目指すことの重要性について述べられた。
フォーラムでは,園田智昭副会長(慶応義塾大学)から開催挨拶があり,続いて大阪成蹊短期大学 武蔵野實学長より歓迎の挨拶を頂いた。武蔵野学長は挨拶の中で,大阪成蹊大学・短期大学の歴史や建学の精神について触れられ,今回のフォーラムにおける発表内容との関連で,自然環境における長期的最適条件を守りながら,経済的な短期的最適条件を目指すことの重要性について述べられた。 景山氏はまず,環境変化が激しく,リスクが複雑化,多様化している現代では,企業価値を高めるためにリスクマネジメント(RM)を導入することが重要であり,RMのPDCAサイクルに管理会計が関わるべきであると述べた。そして,RMと管理会計との関わりをカリフォルニア州立大学バークレー校の事例研究において考察するという本報告の目的を示した。
景山氏はまず,環境変化が激しく,リスクが複雑化,多様化している現代では,企業価値を高めるためにリスクマネジメント(RM)を導入することが重要であり,RMのPDCAサイクルに管理会計が関わるべきであると述べた。そして,RMと管理会計との関わりをカリフォルニア州立大学バークレー校の事例研究において考察するという本報告の目的を示した。 平井氏は,まず企業価値の測定におけるインタンジブルズ情報の把握の重要性について述べ,インタンジブルズ情報の一つとしての人的資本,特に従業員満足度に関する情報と企業価値との関連性について検証を行うという研究目的を示した。次に,先行研究のレビューを通して,日本と米国における人的資産に関する考え方に差異があることを指摘しながらも,経営上重要な要因であることを再認識することの重要性を指摘した。
平井氏は,まず企業価値の測定におけるインタンジブルズ情報の把握の重要性について述べ,インタンジブルズ情報の一つとしての人的資本,特に従業員満足度に関する情報と企業価値との関連性について検証を行うという研究目的を示した。次に,先行研究のレビューを通して,日本と米国における人的資産に関する考え方に差異があることを指摘しながらも,経営上重要な要因であることを再認識することの重要性を指摘した。 観光は現在,重要な国家戦略として位置づけられているが,環境破壊などの負の影響が存在することが課題として指摘されている。イギリスでは1999年頃から,人々の「幸せ」という価値観に焦点が当てられており,経済的な側面だけでなく,持続可能な発展に関して多様な研究結果が報告されている。ただし,持続可能な発展を実践していく立場である小規模ツーリズムとホスピタリティ企業の研究は少数であるため,奈良県の小規模宿泊施設経営者を対象としたアンケート調査により,経営者の観光開発に対する態度,認識,経営行動の構造を明らかにするという研究目的を示した。
観光は現在,重要な国家戦略として位置づけられているが,環境破壊などの負の影響が存在することが課題として指摘されている。イギリスでは1999年頃から,人々の「幸せ」という価値観に焦点が当てられており,経済的な側面だけでなく,持続可能な発展に関して多様な研究結果が報告されている。ただし,持続可能な発展を実践していく立場である小規模ツーリズムとホスピタリティ企業の研究は少数であるため,奈良県の小規模宿泊施設経営者を対象としたアンケート調査により,経営者の観光開発に対する態度,認識,経営行動の構造を明らかにするという研究目的を示した。 本報告において,まず,島氏は非財務指標の重要性を示すためには,非財務指標が持つ財務業績の説明力について示す必要があり,そのために,国立病院で行われてきた患者満足度調査の結果を通じて,国立病院の収益,費用,利益の変動について分析するという研究目的を示した。次に,先行研究のレビューにより非財務指標と財務成果の変動との関係について検証するという目的には,顧客満足度を非財務指標として用いることが適切であると述べた。
本報告において,まず,島氏は非財務指標の重要性を示すためには,非財務指標が持つ財務業績の説明力について示す必要があり,そのために,国立病院で行われてきた患者満足度調査の結果を通じて,国立病院の収益,費用,利益の変動について分析するという研究目的を示した。次に,先行研究のレビューにより非財務指標と財務成果の変動との関係について検証するという目的には,顧客満足度を非財務指標として用いることが適切であると述べた。 次に,安酸氏は本報告におけるパネル分析の方法を3つ示し,それぞれの分析における推定結果を示した。そして,その結果によって得られるインプリケーションは満足度指標に「全体として病院に満足」という回答を採用した場合と,「家族や知人に勧めたい」という回答を採用した場合とで大きく異なると述べた。安酸氏によれば,前者の場合は,(1)満足度の向上はコストには影響しない,(2)入院患者の満足度は病院の財務面に影響しない,(3)相対的に高い満足度をさらに高めることは収益にマイナスの影響を及ぼすというインプリケーションが,後者の場合は,(1)外来患者の満足度はコストに影響する,(2)入院患者満足度は病院の財務面に影響する,(3)相対的に高い満足度を高める努力は病院の収益にプラスの影響をもたらすというインプリケーションが得られるということであった。
次に,安酸氏は本報告におけるパネル分析の方法を3つ示し,それぞれの分析における推定結果を示した。そして,その結果によって得られるインプリケーションは満足度指標に「全体として病院に満足」という回答を採用した場合と,「家族や知人に勧めたい」という回答を採用した場合とで大きく異なると述べた。安酸氏によれば,前者の場合は,(1)満足度の向上はコストには影響しない,(2)入院患者の満足度は病院の財務面に影響しない,(3)相対的に高い満足度をさらに高めることは収益にマイナスの影響を及ぼすというインプリケーションが,後者の場合は,(1)外来患者の満足度はコストに影響する,(2)入院患者満足度は病院の財務面に影響する,(3)相対的に高い満足度を高める努力は病院の収益にプラスの影響をもたらすというインプリケーションが得られるということであった。 伊藤氏は,まず行財政改革の取り組みを中心に市川市の状況を述べたうえで,その取り組みのひとつである市川市版ABCについて詳細に報告した。市川市版ABCの特徴として,分析自体にかかるコストが大きいことといった一般的なABCのデメリットを解消するため,総コストではなく職員の活動量に着目し,業務ごとの活動従事量を把握し,特に定型的業務の詳細な活動量を対象としていることを述べた。市川市では,市川市版ABCをシステム化し,各職員からのデータ収集を行い,職員個人レベルの活動までデータ化することにより,市民サービス直結業務と内部管理事務の活動量の詳細が可視化されていることを説明した。そして,市川市版ABCから導かれる効果として,内部管理事務や定型的業務をできるだけ効率的にしつつ,市民サービス直結業務に人材を再配置でき,市民サービスを維持しつつ,コストの削減が可能となることを示した。さらに,伊藤氏は,市川市市政戦略会議による,事業仕分け(平成22年度)と施設の有効活用にかかる公開検討会(平成23年度)についても報告した。はじめに,事業仕分けの実施内容を説明し,事業の可視化の進展といった効果や,結果が極端になるといった課題を示した。つぎに,施設の有効活用にかかる公開検討会の実施内容を説明したうえで,事業仕分けと施設の有効活用にかかる公開検討会を比較し,前者が事業の量的な側面からのアプローチ,後者が事業の質的な側面からのアプローチとして検討するために適している可能性を指摘した。
伊藤氏は,まず行財政改革の取り組みを中心に市川市の状況を述べたうえで,その取り組みのひとつである市川市版ABCについて詳細に報告した。市川市版ABCの特徴として,分析自体にかかるコストが大きいことといった一般的なABCのデメリットを解消するため,総コストではなく職員の活動量に着目し,業務ごとの活動従事量を把握し,特に定型的業務の詳細な活動量を対象としていることを述べた。市川市では,市川市版ABCをシステム化し,各職員からのデータ収集を行い,職員個人レベルの活動までデータ化することにより,市民サービス直結業務と内部管理事務の活動量の詳細が可視化されていることを説明した。そして,市川市版ABCから導かれる効果として,内部管理事務や定型的業務をできるだけ効率的にしつつ,市民サービス直結業務に人材を再配置でき,市民サービスを維持しつつ,コストの削減が可能となることを示した。さらに,伊藤氏は,市川市市政戦略会議による,事業仕分け(平成22年度)と施設の有効活用にかかる公開検討会(平成23年度)についても報告した。はじめに,事業仕分けの実施内容を説明し,事業の可視化の進展といった効果や,結果が極端になるといった課題を示した。つぎに,施設の有効活用にかかる公開検討会の実施内容を説明したうえで,事業仕分けと施設の有効活用にかかる公開検討会を比較し,前者が事業の量的な側面からのアプローチ,後者が事業の質的な側面からのアプローチとして検討するために適している可能性を指摘した。 渡邊氏は,まずBSCに関する研究を参照し,わが国医療組織において多面的な目標達成につながる組織成員の心理構造を解明するという研究目的を示した。そのうえで,先行研究における理論的背景を踏まえ,組織成員の目標達成,行動意識(財務意識,患者意識,学習意識),および自律性の関係について理論モデルを構築し,それに基づく複数の仮説を提示した。そして,渡邊氏は,敬愛会中頭病院・ちばなクリニックと福井県済生会病院に対する経年的アンケート調査から得られたデータをサンプルとし,共分散構造分析によってこれらの仮説を検証した。分析の結果,次の4つの発見事項を指摘した。第1に,学習意識は業務に対する自律性から正の影響を受ける。第2に,財務意識と患者意識は,学習意識から正の影響を受ける。第3に,BSCの4つの視点に対する目標達成は,学習意識と財務意識から正の影響を受ける。第4に,目標達成に対しては,学習意識から財務意識と患者意識を媒介した間接効果よりも,学習意識からの直接効果のほうが相対的に強い影響を及ぼす。
渡邊氏は,まずBSCに関する研究を参照し,わが国医療組織において多面的な目標達成につながる組織成員の心理構造を解明するという研究目的を示した。そのうえで,先行研究における理論的背景を踏まえ,組織成員の目標達成,行動意識(財務意識,患者意識,学習意識),および自律性の関係について理論モデルを構築し,それに基づく複数の仮説を提示した。そして,渡邊氏は,敬愛会中頭病院・ちばなクリニックと福井県済生会病院に対する経年的アンケート調査から得られたデータをサンプルとし,共分散構造分析によってこれらの仮説を検証した。分析の結果,次の4つの発見事項を指摘した。第1に,学習意識は業務に対する自律性から正の影響を受ける。第2に,財務意識と患者意識は,学習意識から正の影響を受ける。第3に,BSCの4つの視点に対する目標達成は,学習意識と財務意識から正の影響を受ける。第4に,目標達成に対しては,学習意識から財務意識と患者意識を媒介した間接効果よりも,学習意識からの直接効果のほうが相対的に強い影響を及ぼす。 大西氏は,まず公共部門の管理会計における今後の課題について,組織マネジメント,政策マネジメント,投融資等マネジメントの3つに分けて整理・提示した。これまで管理会計が活用されてきた組織マネジメントだけではなく,政策マネジメントにおける業績測定や,投融資等マネジメントにおける財政投融資・政策金融,さらにはPFI等といった領域への管理会計の活用可能性を示した。そして,国税組織などを調査対象とした組織マネジメントのケース・スタディについて報告し,公共部門においてもABM,ABC,BSCといった管理会計手法に近い実務が行われていることを明らかにした。これらのケース・スタディに基づき,ABMなどのさまざまな管理会計手法を公共部門の効率性と効果性に関連づけた基本モデルを提示した。また,日本だけではなく,各国の労働集約的な公共部門の管理会計の実態も示した。さらに,大西氏は,管理会計手法等の導入プロセスについても報告した。管理会計手法等の導入プロセスについて,ABMの導入を起点にミクロへの展開とマクロへの展開を説明したうえで,導入に際して重要になる要因として,人事権とリンクしたリーダーシップの継続,全体像を踏まえたうえでの漸進的な導入,組織の損得勘定への働きかけなどを明らかにした。
大西氏は,まず公共部門の管理会計における今後の課題について,組織マネジメント,政策マネジメント,投融資等マネジメントの3つに分けて整理・提示した。これまで管理会計が活用されてきた組織マネジメントだけではなく,政策マネジメントにおける業績測定や,投融資等マネジメントにおける財政投融資・政策金融,さらにはPFI等といった領域への管理会計の活用可能性を示した。そして,国税組織などを調査対象とした組織マネジメントのケース・スタディについて報告し,公共部門においてもABM,ABC,BSCといった管理会計手法に近い実務が行われていることを明らかにした。これらのケース・スタディに基づき,ABMなどのさまざまな管理会計手法を公共部門の効率性と効果性に関連づけた基本モデルを提示した。また,日本だけではなく,各国の労働集約的な公共部門の管理会計の実態も示した。さらに,大西氏は,管理会計手法等の導入プロセスについても報告した。管理会計手法等の導入プロセスについて,ABMの導入を起点にミクロへの展開とマクロへの展開を説明したうえで,導入に際して重要になる要因として,人事権とリンクしたリーダーシップの継続,全体像を踏まえたうえでの漸進的な導入,組織の損得勘定への働きかけなどを明らかにした。